2020年04月21日

多くの中小企業経営者にとっての最大の悩みは資金繰りです。毎月の家賃の支払い、社員や従業員への給与の支払い、銀行など金融機関への借り入れの返済など、様々な支払いのための資金繰りに奔走しなければなりません。どうにか月末までに支払いが間に合ったかと思ったら、また翌月の支払いのための資金繰りを考えなくてはなりません。
こうして1年があっという間に過ぎていきます。そして最後に待っているのが、法人税など税金の支払いです。しかし、月々の支払いにも四苦八苦して資金繰りが難しいのに、このような法人税などの税金の支払いにまで手が回らない経営者も少なくありません。滞納したらいくら延滞税がかかるのか、差し押さえられたりしないか不安でたまりません。ここではそうした不安を解消するための対処法について、徹底解説していきます。
法人税とは
法人税とは、株式会社や合同会社などの法人が、事業活動によって得た所得(利益)に対して課せられる国税です。毎事業年度の所得金額を計算し、その金額に応じて納税する仕組みとなっており、会社の規模や資本金の額によって税率が変動します。企業活動を営むうえでは避けては通れない税金であり、事業の成長や経営の健全性とも密接に関わっています。
税率について
法人税の税率は、資本金1億円以下の中小法人で年800万円以下の所得には15%(軽減税率)、800万円を超える部分や普通法人(中小法人以外)については23.2%(2025年6月現在)が適用されます。加えて、地方法人税も課されるため、実効税率は30%前後となるケースが一般的です。具体的な税率や適用範囲は法改正により変動するため、最新の情報を確認しましょう。
| 区分 | 適用税率 | ||
|---|---|---|---|
| 資本金1億円以下の法人など | 年800万円以下の部分 | 下記以外の法人 | 15% |
| 適用除外事業者(※) | 19% | ||
| 年800万円超の部分 | 23.2% | ||
| 上記以外の普通法人 | 23.2% | ||
支払義務について
法人税は、会社が利益を得た場合はもちろん、赤字であっても申告そのものは必須です。納税義務は法人そのものに課せられており、代表者や取締役個人が直接責任を負うわけではありません。ただし、倒産や清算などの場合には清算人が第二次納税義務者となることもあります。
期限について
法人税の申告と納付の期限は、原則として決算日から2カ月以内に設定されています。たとえば、3月決算の企業であれば、5月末までに申告・納付しなければなりません。申告や納付が遅れると、延滞税や無申告加算税などが発生するため注意が必要です。
どうしても期限までに納付が難しい場合は、早めに税務署へ相談し、納税猶予制度などの活用を検討しましょう。
法人税等とは
「法人税等」とは、法人税だけでなく、法人住民税や法人事業税も含めた法人が納付する税金の総称です。以下のものが挙げられます。
| 法人住民税 | 会社の所在地(都道府県・市区町村)ごとに課される地方税です。法人税額に連動して税額が決まる「法人税割」と、資本金等に応じた「均等割」で構成されます。 |
|---|---|
| 法人事業税 | 都道府県が課税する地方税で、法人の所得金額に応じて課されます。所得だけでなく、特定の外形基準(資本金や付加価値額など)を用いることもあります。 |
これらは法人税と同時期に申告・納付が必要となるため、経営計画や資金繰りに影響を与える可能性があります。
法人税が払えないままにしてくと起きること
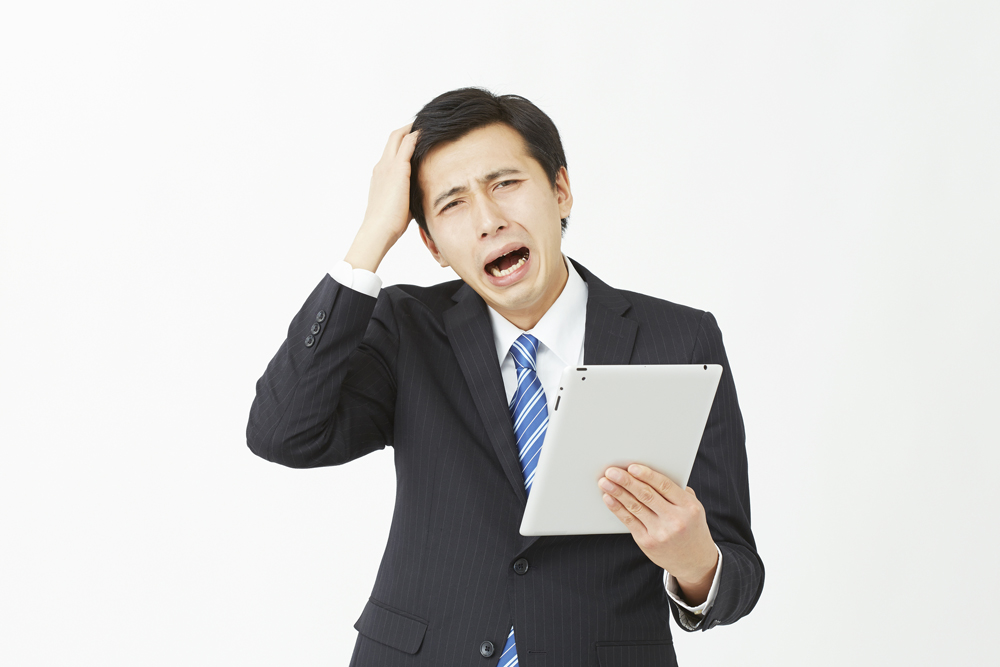 滞納とは、支払うべき税金を納付期限までに納めないことですが、納付期限を1日でも超えてしまうと滞納とされてしまいます。ただ、滞納だからといって、直ちに財産を差し押さえられるわけではありません。
滞納とは、支払うべき税金を納付期限までに納めないことですが、納付期限を1日でも超えてしまうと滞納とされてしまいます。ただ、滞納だからといって、直ちに財産を差し押さえられるわけではありません。
滞納から差し押さえまでには一定の手順があり、それに従って手続きが進められていきます。一般的な手順としては次のような流れになります。
- 督促状の送付(納付期限から50日以内)
- 電話や書面による催促、あるいは担当職員の訪問
- 滞納者の財産その他についての情報収集
- 催促に応じない場合に差し押さえ
- 差し押さえ財産の公売と換価
- 税金充当と残金の滞納者への配当
法人税が払えないときの罰則とリスク
法人税を支払わなかった場合、納税遅延に対しては延滞税や加算税などのペナルティが科されます。さらに、税務署からの督促や財産の差押え、預金口座の凍結といった強制執行のリスクも生じます。加えて、企業の信用力低下や、金融機関・取引先からの信頼喪失といった経営リスクにも直結するため、早めの対応が極めて重要です。
| 罰則 |
督促状 |
|---|---|
|
延滞税 ①法定の納付期限の翌日から、2ヶ月までの期間については、「年率7.3%」あるいは、「特例基準割合+1%」のいずれか低い利率を納付すべき税額に乗じる ※「特例基準割合」とは、各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12除して得た割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合です。 |
|
|
税務調査 |
|
|
資産の差し押さえ |
|
| リスク |
融資/補助金が受けられない |
|
貸しはがし |
|
|
企業信用度の低下 |
|
|
生産力の低下/キャッシュフローの悪化 |
法人税が払えない場合の対処法
 パンデミックなどと呼ばれる今回の新型コロナウイルスによる急激な景気悪化などは、経営者の努力ではどうにもなりません。悪いことに今年は2月、3月といった多くの会社にとっての決算、確定申告にあたってしまいました。手元資金がショートしてしまった会社も少なくなく、法人税その他の税金が払えない状況です。
パンデミックなどと呼ばれる今回の新型コロナウイルスによる急激な景気悪化などは、経営者の努力ではどうにもなりません。悪いことに今年は2月、3月といった多くの会社にとっての決算、確定申告にあたってしまいました。手元資金がショートしてしまった会社も少なくなく、法人税その他の税金が払えない状況です。
法人税の法定納付期限は、決算から2ヶ月以内となっていますから、このままではかなりの会社は法人税などが支払えず滞納となってしまいます。今回は、国も様々な特例措置を行って対応していますが、通常、このように法人税などが支払えず滞納してしまった場合に、考えられる対処法にはどのようなものがあるか見ていきます。
まず考えられるのが税務署への直接相談、そして納税の猶予や差し押さえから換価までの猶予申請といったものです。
税務署への直接相談
このような国税における猶予制度により、滞納処分としての差し押さえや公売・換価といった最悪の自体は回避できますが、これらの猶予申請に先立って、所轄の税務署への直接相談が極めて重要になります。
差し押さえなどの滞納処分を回避するためのポイントは、なんといっても督促状が送付されるタイミングです。先にも述べたように、督促状が送付された日から10日以内に滞納している税金を完納しないと、税法上では差し押さえが可能になってしまいます。ただあくまで原則であって、直ちに差し押さえられるといった処分はありません。
だからといっていつまでも放置していてはいけません。督促状を受けたら、まず所轄の税務署に問い合わせたり、直接訪問して相談することです。税務署の職員も人間ですから、誠実な態度で納税の意思を示せば、延滞税を含め一括での支払いを請求することはありません。分割による納税や金銭以外での物納に応じてくれることも少なくありません。
納税の猶予申請
 法人税のような国税には、「猶予制度」というものがあります。これは一定の要件に該当する場合、税務署に申請して認められると、納税や差し押さえによる換価などが猶予されるというものです。まず、納税の猶予申請から見ていきます。
法人税のような国税には、「猶予制度」というものがあります。これは一定の要件に該当する場合、税務署に申請して認められると、納税や差し押さえによる換価などが猶予されるというものです。まず、納税の猶予申請から見ていきます。
納税の猶予の要件
災害、事業の休業や廃業、納税者や生計を一にしている家族の病気等の理由で、法人税などの国税を一時に納付できないと税務署から認められた場合、あるいは、本来の納付期限から1年以上経過したあと、確定した税額を一時に納付することができないと認められた場合などに、納税の猶予申請ができます。
納税の猶予の効果
納税の猶予が認められると、まず新たな差し押さえ、公売・換価といった滞納処分が執行されることはありません。また、すでに差し押さえられている財産がある場合でも、税務署に申請すれば、差し押さえが解除されることもあります。そして、認められた納税猶予の期間中の延滞税の全部または一部が免除されます。
このようにかなりの猶予の効果や待遇を受けられますから、この期間に納税資金を確保し、支払いを完了することです。
納税の猶予手順の流れ
納税の猶予を受ける一般的な流れについては次のようになります。
- 「猶予申請書(猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合と100万円超の場合がある)」、担保を要する場合の「担保提供書」などの書類の作成と提出。
- 提出された書類等の審査、補正がある場合、補正通知書の送付(送付を受けた翌日より20日以内に補正されないと申請の取り下げとみなされる)。
- 審査の結果、猶予の許可がされた場合「納税の猶予許可通知書」が申請者に送付され、「分割納付計画」に沿った納付を行う。
審査の結果、猶予が不許可となる場合もあります。主な理由としては、猶予の要件に該当しない、猶予期間内に完納することができないと認められる時、審査の際、税務署職員の質問に回答しないなど。あるいは、不当な目的による申請など誠実になされた申請でないときなども猶予不許可となります。
納税の猶予が許可されたあとでも、猶予期間内での完納ができないと認められたり、分割納付計画通りの納付がなされない、不正な手段による猶予申請が許可されたことが判明したなどの理由で納税の猶予が取り消されたり、猶予期間が短縮されることもあります。この場合、不服申し立てをすることができます。
納税猶予期間
納税の猶予を受けることができる期間は、1年の範囲内で、申請者の財産や収支の状況に応じて、最も早く完納することができる期間となっています。また、当初の猶予期間と合わせて最長2年以内の範囲で猶予期間の延長が認められることもあります。
換価の猶予申請
換価の猶予の要件
換価の猶予を受けるための主な要件としては、以下のようなものがあります。
- 法人税などの国税を一時に納付することにより、事業の継続や生活の維持を困難にするおそれがあると認められること。
- 納税について誠実な意思を有すると認められること。
- 法定納付期限の6ヶ月以内に「換価の猶予申請書」を所轄の税務署に提出していること。
- 猶予を受けようとする金額に相当する担保の提供があること。
換価の猶予の効果
換価の猶予が認められると、すでに差し押さえられている財産の公売と換価が猶予されます。また、差し押さえにより、事業の継続や生活の維持を困難にするおそれがある財産についての差し押さえが猶予されることもあります。そして、換価の猶予が認められた期間は延滞税の一部が免除されます。
なお、換価の猶予における手順の流れや猶予期間については、納税の猶予の場合と同様になっています。こうした猶予期間内に法人税の全額が納付された場合、延滞税の全部一部が免除されることになります。
ファクタリングを利用する
税務署に相談し、納税や換価の猶予を受けながら、猶予期間に完納するわけですが、その際の納税資金をどこから調達するかも考えておかなくてはなりません。日々の経営の中で現金収支をしっかり管理し、捻出できればそれに越したことはありませんが、数ヶ月の猶予期間であればファクタリングを利用してもよいでしょう。
ファクタリングとは、手元にある売掛債権をファクタリング会社という買取り会社に売却・譲渡するものです。手数料分が割引かれ、残額を受け取るものです。短期の資金調達のためには有効ですが、比較的新しい資金調達手段のため、法の整備も完全ではなく悪徳業者もあります。そのため、利用に際しては事業者の事前調査をしっかり実施しておく必要があります。
会社の決算が黒字でも、月々の仕入れ代金の支払いや銀行への借り入れ返済などで手元のキャッシュフローが十分でなく、法人税などの税金の支払いにまで手が回らないといった中小企業の経営者も少なくありません。そうこうしているうちに納付期限がすぎ、督促状が送付されてきます。
ただ、督促状が送付されても直ちに財産を差し押さえられることは通常ありません。まずやるべきことは、所轄の税務署に直接相談に行き、納税や換価の猶予を受け、納付計画書に沿って確実に納付していくことです。
大切なことは、督促状や催促通知などを無視せず、誠実な態度で納税の意思を示すことです。
法人税が払えない方からのよくある質問
法人税の納付に悩む経営者の方からは払えない場合の具体的な対応や廃業した場合の納税義務、分割払いの可否、時効の有無など、さまざまな質問が寄せられます。ここでは今までいただいた代表的なご質問と回答をまとめました。
廃業した場合はどうなりますか?
法人を廃業して清算手続きや破産手続きを進めたとしても、税法上は法人が存続し続けるため、納税義務も残ります。最終的には清算人が第二次納税義務者となり、残った資産の中から税金を優先的に支払う必要があります。
法人税には時効はないですか?
法人税の滞納は原則5年で時効が成立しますが、税務署が差し押さえや督促などの法的手続きを行うことで時効が停止する場合も多いです。納税猶予申請や差押え等があれば、その間は時効のカウントが一時的に中断されるため、実際に時効が成立するケースは稀です。
分割払いはできますか?
法人税を一括で納付することが難しい場合、税務署に「納税の猶予」や「換価の猶予」を申請することで、分割納付が認められることがあります。これらが認められれば、資金繰りへの負担を一定程度和らげることが可能です。まずは税務署に相談しましょう。
税務署との交渉は可能ですか?
税務署は未納の法人税を1円でも多く回収したいという意向があるため、基本的には納税に関する交渉を拒絶することはまずありません。実際の納付可能額や分割条件などについて、真摯に事情を説明することで柔軟に対応してもらえる場合も多いです。
先々の資金繰りにお困りの方
法人税をはじめとした納税資金の調達が困難な場合は、早めに専門家や経営支援機関へ相談することが大切です。税務署との交渉や納税猶予申請、経営改善計画の策定など、事前に手を打つことでリスクを最小限に抑えることができます。状況が深刻化する前に、信頼できる専門家へ相談し、事業継続の道筋を探しましょう。
東京事業再生コンサルティングセンターでは法人税の納税に関するお悩みごとはもちろん、根本的な解決、つまり事業再生までアドバイスさせていただきます。1年間は無料でコンサルティングサービスをご提供します(条件あり)。ぜひお一人で抱え込まず、まずはお話をお聴かせください。
«前へ「赤字でも納める税金とは!?節税対策についても徹底解説」 | 「【20年6月最新】「新型コロナウイルス感染症特別貸付」の審査通過率をUPさせる方法を徹底解説」次へ»
本コラムの監修者

事業再生コンサルタント
清水 麻衣子
元銀行マンで、多くの顧客の相手をしてきた実績と数々の中小企業を見てきた知見をもって、東京事業再生コンサルティングのコンサルタントへ。
通常のコンサル会社におけるコンサルタントとは大きく違い、豊富な知識と現場のリアルを把握している、企業を想った本質的なコンサルが魅力。
関連コラム
-
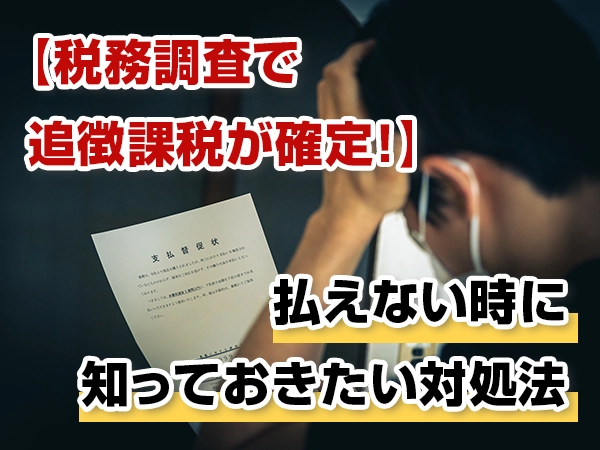
【税務調査で追徴課税が確定!】払えない時に知っておきたい対処法
-
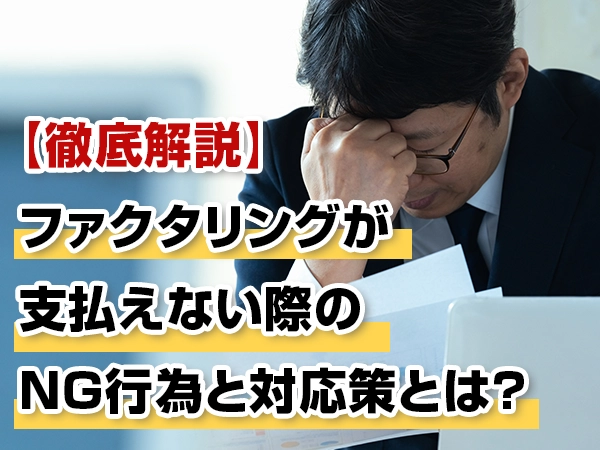
【徹底解説】ファクタリングが支払えない際のNG行為と対応策とは?
-
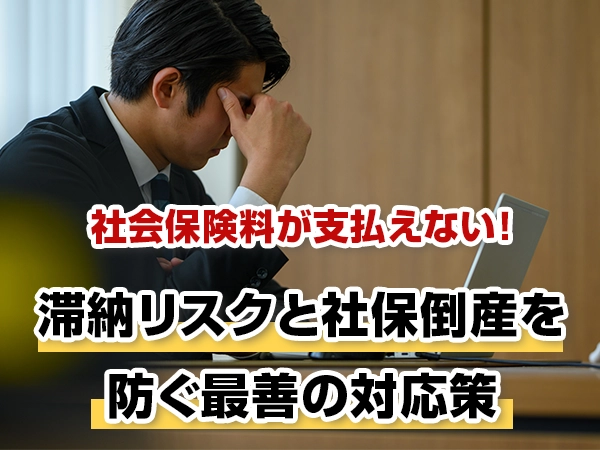
社会保険料が支払えない!滞納リスクと社保倒産を防ぐ最善の対応策
-
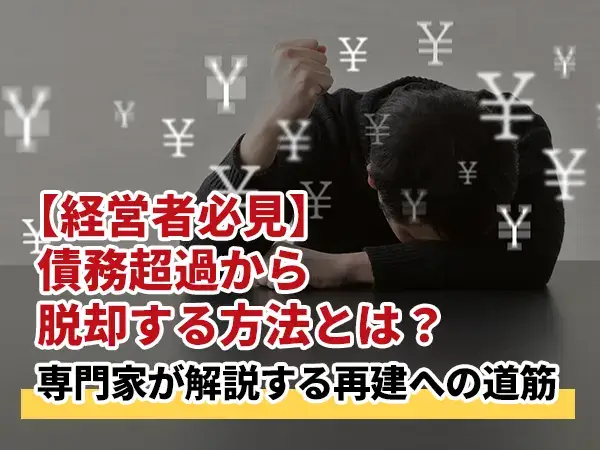
【経営者必見】債務超過から脱却する方法とは?専門家が解説する再建への道筋
-

保証協会から融資を断られたら?審査通過のための攻略法
-
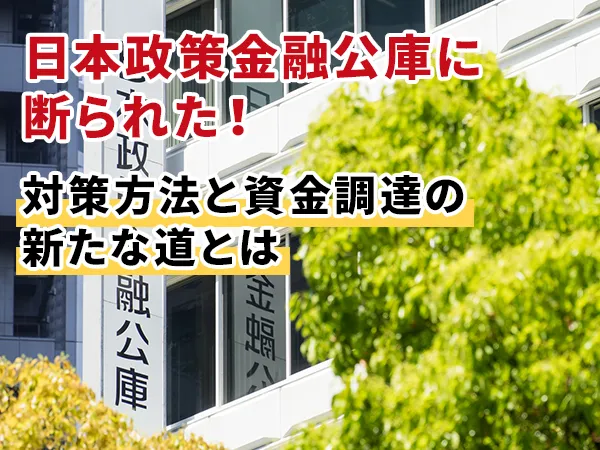
日本政策金融公庫に断られた! 対策方法と資金調達の新たな道とは


 1年間無料コンサル
1年間無料コンサル
当社は、若くして起業したり後継者となった方々、本気で事業を立て直したいと強く想っている方々を全力でサポートします。