2025年07月25日
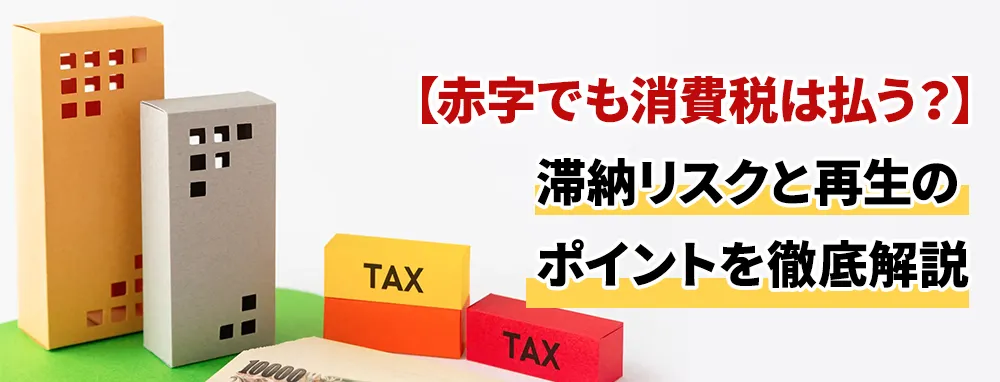
「赤字経営で消費税が払えない」「このままでは会社が破綻してしまうのではないか」……多くの中小企業経営者が、消費税の納付を前にして深刻な悩みを抱えています。
利益が出ていなくても消費税は納めなければならず、滞納すれば事業再生どころか経営破綻のリスクも高まります。この記事では、赤字経営の会社が消費税の支払いで直面する課題とリスク、現実的な対策や事業再生への具体的な道筋を詳しく解説します。
多くの赤字企業経営者が抱える消費税に対する切実な悩み
 多くの中小企業経営者は、売上の減少や経費の増加により赤字が続き、資金繰りの厳しさに直面しています。そんな中で、もっとも頭を悩ませるのが「赤字なのに消費税の納税義務がある」という現実です。その年度に利益が出ていなかったとしても、前期に売上があれば消費税から逃れることはできません。
多くの中小企業経営者は、売上の減少や経費の増加により赤字が続き、資金繰りの厳しさに直面しています。そんな中で、もっとも頭を悩ませるのが「赤字なのに消費税の納税義務がある」という現実です。その年度に利益が出ていなかったとしても、前期に売上があれば消費税から逃れることはできません。
資金が底を突きかけている経営者にとって、消費税の納付通知は重くのしかかります。もし納めきれなければ、会社の信用を失い、最悪の場合は経営破綻という道も現実味を帯びてきます。事業再生や経営改善の道を模索している最中に消費税の壁にぶつかってしまうというケースは決して少なくありません。
なぜ赤字なのに消費税を払う必要があるのか?
会社は赤字なのに、なぜ消費税だけは納めなくてはならないのか?これは多くの赤字企業経営者が抱く、素朴で切実な疑問です。利益が出ていないのだから、当然税金も発生しないと考えてしまうのは無理もありません。
しかし、消費税は法人税や所得税とはまったく異なる性質を持っています。この違いが、赤字企業の資金繰りをさらに苦しめているのです。まずは消費税の仕組みと資金難に陥る原因を押さえておきましょう。
赤字企業を悩ませる消費税と税金倒産
赤字経営の企業が消費税を納められず、経営破綻に追い込まれるケースは年々増えています。東京商工リサーチが2024年に発表したデータによると、税金滞納による倒産件数は過去最多を記録しました。コロナ禍を経て売上回復が思うように進まず、赤字決算が続く企業が増加する中、「税金倒産」は他人事ではありません。

出典:株式会社東京商工リサーチ
2025/01/11「「税金滞納(社会保険料含む)」倒産 過去最多の176件 サービス業他や建設業など、労働集約型で増加が目立つ」内
「2024年(1-12月)の全国企業倒産(負債1,000万円以上)のうち、「税金滞納」関連を集計・分析」の調査結果
消費税は売上高に基づいて課されるため、利益が出ていなくても納税義務が発生します。特に消費税は「預かり金」に近い性質を持っているため、国からは「消費者から預かった分を納めるのは当然」という態度で厳しく徴収されます。滞納すれば督促や延滞税、最悪の場合は会社財産の差し押さえも現実となります。赤字経営で資金繰りが厳しい中、消費税の納付が会社存続の分岐点に。これは多くの中小企業が直面する現実的なリスクなのです。
消費税の基本的な仕組み
ここでは、赤字経営の会社でも必ず理解しておくべき消費税の仕組みについて、わかりやすく説明します。消費税は、売上や利益の大小に関係なく、売上が一定額を超えれば必ず納めなければならない税金です。法人税や所得税とは違うルールがあることを理解することが、今後の資金繰りや経営判断の第一歩になります。
消費税と法人税・所得税の違い
消費税と法人税・所得税の違いを正しく理解していないと、誤った経営判断をしてしまう危険があります。消費税は「間接税」と呼ばれ、商品やサービスを販売したときに発生します。一方、法人税は「会社が出した利益」に対して課される直接税、所得税は「個人が得た収入」に課される直接税です。
消費税は売上のある事業者が納税義務者となり、たとえ会社が赤字でも売上高が一定額を超える場合、納付しなければなりません。
| 項目 | 消費税 | 法人税 | 所得税 |
|---|---|---|---|
| 税の性質 | 間接税 | 直接税 | 直接税 |
| 課税対象 | 商品・サービスの販売や提供(売上) | 法人の所得(利益) | 個人の所得(給与、事業所得など) |
| 納税義務者 | 商品・サービスを提供した事業者 | 法人 | 個人(会社員、個人事業主など) |
| 実質負担者 | 商品・サービスを購入した消費者 | 法人 | 個人(会社員、個人事業主など) |
| 利益との関連性 | 会社の利益(黒字・赤字)とは直接関係なし。 売上があれば納税義務発生。 |
会社の利益に直接連動。 赤字なら原則納税なし。 |
個人の所得に直接連動。 所得が多ければ税額も増加。 |
| 主な特徴/補足事項 | ・預かり金としての性格 ・仕入税額控除制度あり ・免税事業者制度あり |
・黒字の場合に納税義務発生 ・繰越欠損金制度あり |
・超過累進課税制度を採用 ・各種控除制度あり |
法人税・所得税は利益や所得があってはじめて課税され、赤字なら納税はありません。対して、消費税は「赤字黒字に関係なく発生する税」です。この点が赤字企業にとって消費税が大きな負担となる理由です。
「赤字経営だから消費税もゼロ」ではない理由
「うちは赤字なんだから、消費税も払わなくていいのでは?」と思われがちですが、それは大きな誤解です。消費税は「消費者から一時的に預かっているお金」という側面があり、企業がそのまま使ってしまうことは認められていません。
消費税は「売上にかかる消費税」から「仕入や経費で支払った消費税」を差し引いた額を納める仕組みです。つまり、売上が発生し、商品やサービスを販売した時点で、その分の消費税を国に納める義務が発生します。たとえ会社の経営が赤字であっても、売上があれば消費税の納付義務が生じるのです。
一方で、法人税や所得税はあくまで「利益」に対して課される税金です。経費が売上を上回る場合、つまり赤字なら納税義務は発生しません。しかし消費税は利益に関係ないのです。「利益が出ていないから消費税も払わなくていい」と考えてしまうと、資金繰りが厳しくなった際に大きなトラブルを招きます。
赤字経営であっても、消費税は確実に納める必要がある。これが多くの経営者にとって“想定外”の負担となっているのです。
赤字経営で消費税を滞納するリスク
消費税の納付が困難になり、支払いを滞納した場合、会社経営に与える影響は非常に大きなものとなります。単なる延滞では済まず、督促や差し押さえ、経営者自身の信用問題にも発展しかねません。ここからは、実際に消費税を滞納した場合に起こりうるリスクや、経営者が背負うことになる法的責任について詳しく解説します。
消費税を滞納するとどうなる?
消費税を滞納すると、まず税務署から督促状が届きます。これを無視した場合、財産の差し押さえなど厳しい措置が取られることもあります。加えて、納付期限を過ぎた分には延滞税が加算され、支払うべき金額が膨らんでいきます。場合によっては、会社の預金口座や売掛金、動産、不動産などが差し押さえられ、資金繰りがさらに悪化することもあります。
また、消費税の滞納情報は信用情報としても記録されるため、取引先や金融機関からの信用も大きく損なわれます。一度滞納が発生すると、経営の立て直しが困難になるため、早期の対応が不可欠です。
経営者の責任と法的リスクの有無
会社が消費税を滞納した場合、原則として納税義務は法人にあります。しかし、悪質な滞納や資産隠しなど、意図的な不正が認められた場合には、経営者個人に対しても法的責任が及ぶ可能性があります。最悪の場合、経営者が連帯納付義務を負ったり、重加算税や刑事罰が課されたりすることもありえます。
また、破産や民事再生手続きの際には、消費税の滞納が再生計画の障害になる場合も多く、事業再生を目指すうえで大きなリスクとなります。経営者は自らの責任を十分理解し、早めに専門家へ相談することが大切です。
【場合別】消費税が払えない時にはどうする?
消費税が払えないという状況は、決して特別なことではありません。しかし、状況によって適切な対応策は異なります。ここからは、「これから払えなくなりそう」「今まさに払えない」「もう資金繰りが限界」といった段階ごとに、現実的な対策や考え方を詳しく紹介します。事業再生や会社の存続に向けて、今できる最善の選択肢を検討しましょう。
「今後払えなくなるかも!」という場合
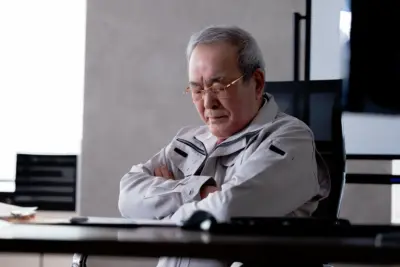 「このままいくと消費税の納付が難しくなりそう」という状況の場合、先回りして対策を講じておくことが重要です。資金繰りの見通しが悪化している段階で手を打てば、最悪の事態を回避できる可能性があります。
「このままいくと消費税の納付が難しくなりそう」という状況の場合、先回りして対策を講じておくことが重要です。資金繰りの見通しが悪化している段階で手を打てば、最悪の事態を回避できる可能性があります。
まずは自社のキャッシュフローを正確に把握し、売上・経費の流れを可視化することから始めましょう。消費税は“預かり金”であるため、本来は納税分を事業資金とは別に管理しておくのが理想です。日々の資金繰りが苦しい場合は、利益の一部を必ず納税用として確保する、足りなくなりそうな場合は経費の削減に着手するなど、今のうちに実行可能な施策を検討しましょう。将来的な納税トラブルを未然に防ぐためには、意識的な資金管理が何よりも大切です。
別口座による強制積み立て
消費税は必ず支払い義務があるものと理解していても、日々の資金繰りの中でつい使い込んでしまうケースは少なくありません。これを防ぐためには、納税資金を“別口座”に強制的に積み立てていくことが効果的です。
具体的には、毎月の売上から消費税相当額を自動的に納税専用口座へ移し、決して事業運転資金と混同しないよう運用します。この方法なら、納税時期がきたときに資金が足りないといった事態を防げます。小規模な企業でも、インターネットバンキングを活用すれば簡単に実践できる方法です。定期的な積立によって納税資金を“見える化”することで、経営者の精神的な負担も軽減されます。
「あとでまとめて払う」のではなく、「毎月少しずつ貯める」という意識が、資金繰りを安定させるポイントです。
人件費の扱いを変える
消費税の納税負担を軽減するために人件費の扱いを工夫するという方法もあります。通常、社員やアルバイトに支払う給与や賞与は消費税の課税対象外ですが、外注費や業務委託費は課税対象となります。たとえば、業務の一部を外部委託(アウトソーシング)することで、仕入税額控除を活用できるケースもあります。
ただし、これはあくまでも事業効率化や適切な人件費管理を目的としたものであり、節税や納税回避のために行うものではありません。安易なコスト削減や形式的な外注化は、逆に労務リスクや法令違反につながることもあるため注意が必要です。専門家に相談し、自社の事業特性や今後の経営方針に合った最適な方法を検討しましょう。
「今!もう払えないよ!」という場合
 「資金繰りが限界で、今すぐ消費税が払えない」という状況に直面している場合、すぐに取るべき行動があります。最も大切なのは、決して納付を放置しないことです。滞納を続けると延滞税や督促、差し押さえなど深刻な事態へと発展しますので、まずは税務署に事情を説明し、支払い猶予や分割納付の申請を検討しましょう。
「資金繰りが限界で、今すぐ消費税が払えない」という状況に直面している場合、すぐに取るべき行動があります。最も大切なのは、決して納付を放置しないことです。滞納を続けると延滞税や督促、差し押さえなど深刻な事態へと発展しますので、まずは税務署に事情を説明し、支払い猶予や分割納付の申請を検討しましょう。
また、事業の現状を正確に把握し、無理のない資金計画を立てることが必要です。取引先や従業員への影響も考慮し、納税資金の調達や、事業再生に向けた具体的なアクションプランの作成も急務となります。いま直面している危機を乗り越えるためには、躊躇せず早めの相談・行動が不可欠です。
公的制度の利用
消費税の納付が一時的に難しい場合、国税庁の「換価の猶予」や「納税の猶予」といった公的制度を活用することができます。「換価の猶予」は、既に滞納が発生した場合に財産の差し押さえを防ぐための制度で、一定の条件を満たせば猶予期間中は分割払いが可能となります。「納税の猶予」は、災害や業績悪化などやむを得ない事情で納税が困難な場合に、申請によって一時的に納付を先延ばしできる制度です。
両者の違いを理解し、自社の状況に合わせて適切な申請を行うことが重要です。公的制度の活用には期限や条件があるため、早めに税務署や専門家に相談しましょう。
それでも期限内納付ができない場合
あらゆる努力をしても、どうしても消費税の期限内納付ができない場合、まずは税務署に納付が遅れる旨を必ず連絡しましょう。無断で滞納した場合と比べ、事情を説明し誠実に対応することで、分割納付や支払い計画の見直しが認められる可能性があります。
安易に放置したり、連絡を怠ったりすると、延滞税の負担が増えるだけでなく、事業再生や経営改善の道が遠のいてしまいます。納付が遅れる事情を丁寧に説明し、支払いの意思があることを示すことが、再生への第一歩です。
「資金繰りが限界だ」消費税の支払いがどうしても困難な場合
「もう会社の資金繰りが限界で、消費税どころか日々の経営もままならない」……そんな危機的状況に陥った場合、自力での再建は極めて困難です。売上の回復が見込めず、借入もできない場合は、まず現実を直視し、今後の事業継続・再生の可能性を冷静に見極めることが大切です。
ここからは、資金調達の具体的手段や、事業再生の専門家に相談するタイミング・重要性について説明します。資金調達や再生スキームを活用し、経営の立て直しを図るための準備を進めましょう。
ファクタリング
納税資金の緊急調達が必要な場合、ファクタリングを活用する手段もあります。ファクタリングとは、会社の売掛債権をファクタリング会社に買い取ってもらい、現金化するサービスです。即時に現金化できるため、資金繰りが厳しい場面で納税資金を確保する手段として活用されています。ただし、ファクタリングには以下のような注意点もあります。
- 手数料が高額になる場合がある
- 悪質な業者によるトラブルが発生する可能性がある
- 契約条件や手数料率を事前に十分確認する必要がある
- そもそも売掛債権がないと利用できない
- 取引先に経営難であることがわかってしまう可能性がある=信用の低下
特に、納税資金調達を目的とした“高額ファクタリング”を提案する業者には注意が必要です。必ず複数社から見積もりを取り、信頼できる専門家に相談しながら進めましょう。
事業再生の専門家への相談
資金調達の手立てが尽き、経営の継続が限界に近づいていると感じたら、速やかに事業再生の専門家へ相談してみましょう。会社の現状を正確に分析し、事業再生計画の策定や債務整理、各種支援制度の活用など、最適な解決策を提案してくれるはずです。
経営者一人で悩みを抱え込むのではなく、早い段階でプロの力を借りることで、再生や再起の道が拓ける可能性が大きく広がります。会社と従業員、取引先の未来、そしてご自身を守るためにも、早めの相談がカギとなります。
赤字経営からの脱却と消費税対策の2つのポイント
 消費税が払えないという悩みは、単に納税資金を用意するだけでは根本解決になりません。大切なのは、赤字からの脱却と、再び同じ状況に陥らないための体質改善です。ここからは、経営改善計画の策定と消費税支払いのための具体的な資金繰り対策、2つの観点から再生への道を解説します。
消費税が払えないという悩みは、単に納税資金を用意するだけでは根本解決になりません。大切なのは、赤字からの脱却と、再び同じ状況に陥らないための体質改善です。ここからは、経営改善計画の策定と消費税支払いのための具体的な資金繰り対策、2つの観点から再生への道を解説します。
①経営改善計画の策定
赤字経営で消費税が払えない状況に直面したら、まずは自社の現状を冷静に分析し、経営改善計画を策定することが重要です。収支構造の見直し、コスト削減、売上拡大の具体策、そして資金繰りの健全化を総合的に進めていきます。
現場レベルの地道な努力と経営者自身の意識改革、そして第三者の視点を取り入れた客観的な分析が、企業再生の第一歩となります。詳しくは以下の記事をご覧ください。
<関連記事>
②消費税の支払いをしっかり行っていくための対策
今後、消費税の支払いが滞らない経営を実現するには、資金繰り管理の徹底が欠かせません。日々のキャッシュフローをリアルタイムで把握し、納税資金を計画的に積み立てることが重要です。
また、資金繰り表の作成や、経営・税務の専門家(税理士やコンサルタント)との定期的なミーティングを通じて、常に自社の財務状況を“見える化”しておくことが再発防止のカギとなります。状況が変わった場合にも素早く対応できる体制を築き、会社の安定経営・成長につなげましょう。
「東京事業再生コンサルティングセンター」なら消費税が払えない状況も解決に導きます
消費税の支払いが難しい、経営改善に行き詰まっている……そんなときは、東京事業再生コンサルティングセンターにご相談ください。
社歴5年以上かつ45歳以下の経営者の方には「コンサル1年無料」の特典を用意。中小企業・赤字企業の事業再生に豊富な実績を持ち、売上拡大ノウハウと「守り」と「攻め」を両立した再生プランをご提案しています。
現状に寄り添い、会社の再建・企業再生を全力でサポートいたします。どんな些細なお悩みでも、まずはお気軽にお問い合わせください。
«前へ「厚生年金が払えない…会社社長が今すぐ取るべき緊急対策を解説」 | 「「資金繰りが限界…」零細企業社長が知っておきたい立て直し方法と改善策」次へ»
本コラムの監修者

事業再生コンサルタント
清水 麻衣子
元銀行マンで、多くの顧客の相手をしてきた実績と数々の中小企業を見てきた知見をもって、東京事業再生コンサルティングのコンサルタントへ。
通常のコンサル会社におけるコンサルタントとは大きく違い、豊富な知識と現場のリアルを把握している、企業を想った本質的なコンサルが魅力。
関連コラム
-
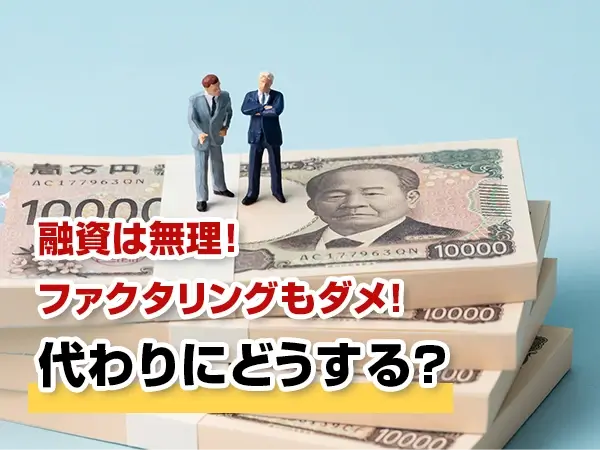
融資は無理!ファクタリングもダメ!代わりにどうする?
-

今すぐ資金繰りを改善したい建設業経営者必見の情報とは
-
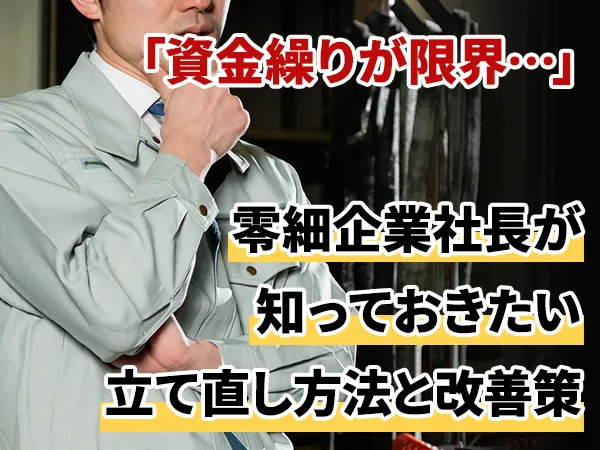
「資金繰りが限界…」零細企業社長が知っておきたい立て直し方法と改善策
-
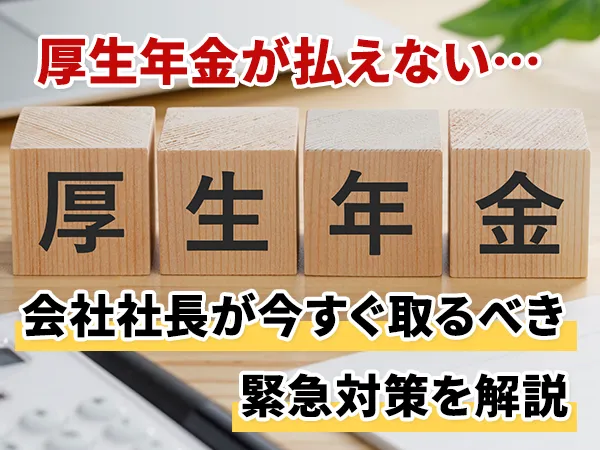
厚生年金が払えない…会社社長が今すぐ取るべき緊急対策を解説
-
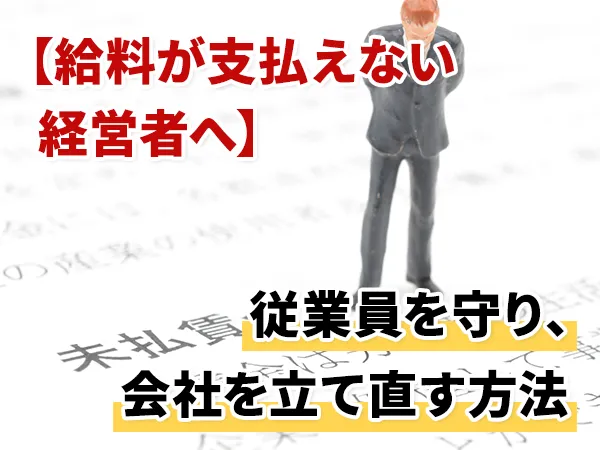
【給料が支払えない経営者へ】従業員を守り、会社を立て直す方法
-
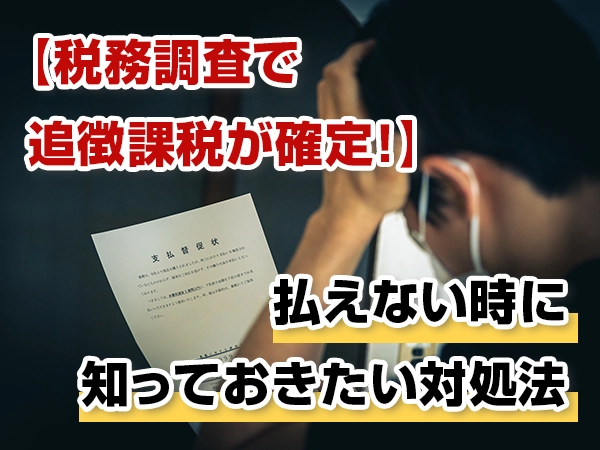
【税務調査で追徴課税が確定!】払えない時に知っておきたい対処法


 1年間無料コンサル
1年間無料コンサル
当社は、若くして起業したり後継者となった方々、本気で事業を立て直したいと強く想っている方々を全力でサポートします。