2025年06月23日
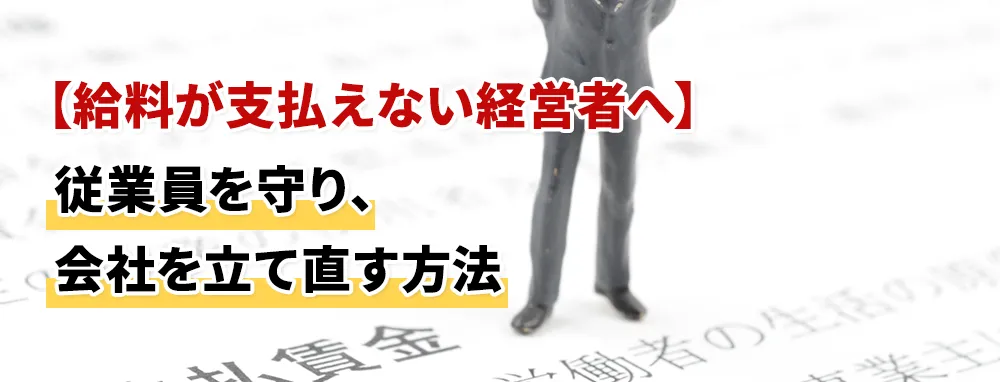
「今月の給料が支払えそうにない」「従業員に納得してもらえるような説明ができない」……経営者として最も重い悩みのひとつが“給料の支払い”です。資金繰りの悪化や突発的なトラブルにより、やむなく給料が払えない状況に陥る事態は、決して他人事ではありません。
本記事では、給料未払いの違法性や経営リスク、実際の事例と原因、そして具体的な対応策や会社再生の道筋まで、徹底的に解説します。
給料未払いは違法?労働基準法の義務と罰則について
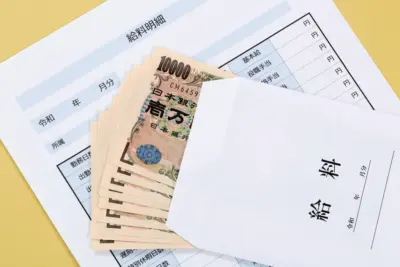 給与の未払いは、「会社が厳しいから仕方ない」「原資がないのだから我慢しろ」では済まされません。賃金の支払いは労働基準法によって厳格に義務と罰則が規定されており、違反すれば刑事責任を問われる重大な問題です。まずは、経営者が最低限知っておくべき「賃金支払いのルール」と違反した場合のリスクを整理していきましょう。
給与の未払いは、「会社が厳しいから仕方ない」「原資がないのだから我慢しろ」では済まされません。賃金の支払いは労働基準法によって厳格に義務と罰則が規定されており、違反すれば刑事責任を問われる重大な問題です。まずは、経営者が最低限知っておくべき「賃金支払いのルール」と違反した場合のリスクを整理していきましょう。
【再確認必須】賃金支払いの5原則
労働基準法第24条には「賃金支払いの5原則」が定められています。経営状況にかかわらず、この原則は“絶対”に守らなければなりません。
- 1 通貨払いの原則
給料は日本円(現金)で支払うのが原則です。例外的に銀行振込も認められていますが、現物や商品券などは原則NGです。 - 2 直接払いの原則
給料は、労働者本人に直接支払わなければなりません。親族や代理人への支払いは原則認められません。 - 3 全額払いの原則
労働者と会社が合意した賃金は、全額を支払う必要があります。法定控除(所得税・社会保険料など)以外の天引きは許されません。 - 4 毎月1回以上払いの原則
給料は必ず「月1回以上」支払うことが義務付けられています。毎月末締め・翌月払いなどは可能ですが、原則として1ヶ月超の遅延は違法です。 - 5 一定期日払いの原則
給与支払い日は、あらかじめ特定の日を定めて、遅延なく支払わなければなりません。会社都合や資金不足を理由に不定期とすることはできません。
これらは労働基準法違反の根拠となり、たとえ一時的な事情でも「仕方なかった」では通りません。
給料の未払は「労働基準法」違法になる!
給与の未払いは明確に労働基準法違反となります。労働基準法第24条(賃金支払い)には、前述の5原則が定められており、これに違反して賃金未払いが生じた場合、経営者や会社には刑事責任が問われる可能性があります。
また、給料未払いは従業員の生活を直撃し、社会的な信用失墜や事業継続そのものの危機にも直結します。
【労働基準法第24条(一部抜粋)】
賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない
経営難であっても、賃金支払いは企業の最重要義務です。従業員からの申告や労働基準監督署の調査により、違反が明らかになると経営者は行政指導、命令、刑事告発を受けるリスクがあります。
給料未払となった場合の刑事罰
給料の未払いは「違法」なだけでは済みません。違反が認められると、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科される可能性があります(労働基準法第120条)。さらに、悪質な場合には刑事告訴や社名公表の対象となることもあります。また、刑事罰が課されるだけでなく、労働基準監督署からの是正勧告や強制調査、最悪の場合は事業の停止命令に発展する事例もあります。
さらに、近年はSNSやインターネットで未払いの事実が拡散しやすくなっており、「社会的制裁」も無視できません。給料未払いも含めて、企業の不祥事は瞬く間に世の中に広まってしまいます。「うちは小規模だから……」「従業員だって会社の状況をわかっているはず」と油断せず、法令順守の意識を強く持つことが求められます。
【実例】給料が払えない会社の実態
給料未払いは決して珍しいトラブルではありません。たとえ大手企業や老舗企業でも、経営難や急な資金ショートにより、従業員への給与支払いができなくなるケースが散見されます。ここからは、最近話題となった事例を紹介します。
①大手脱毛サロンの給料未払事例
大手脱毛サロン(実名非公開)を展開する某社では、急速な店舗拡大による資金繰り悪化を背景に、数百名単位の従業員に対して給料未払いが発生しました。経営陣が従業員に十分な説明や対応をしないまま、SNSなどで未払いの事実が拡散。従業員からは労働基準監督署への相談や一斉退職、集団訴訟が起き、結局その後会社は倒産してしまいました。従業員の生活が守られず、社会的信用も大きく損なわれた事例です。
②建築会社の給料未払事例
ある地方の建設会社では、複数回にわたり給料が遅配・未払いとなり、従業員が一斉に離職。その後、事業継続が困難となり、会社は破産申請に追い込まれました。未払いが続くと経営再建も難しく、倒産リスクが急激に高まる現実を物語るケースです。特に技術や知識が豊富な従業員が退職してしまうとなると、一気に事業が行き詰まってしまいます。
給料が払えない主な理由3選
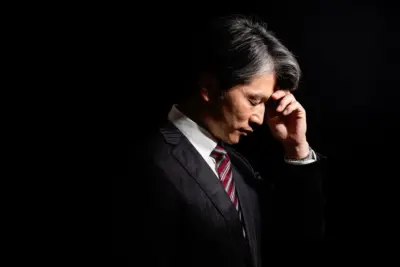 実際に会社が給料を払えなくなる原因はさまざまです。多くの場合、原因は1つではなく、複数の要因が複雑に絡み合って発生します。ここからは代表的な理由を3つ見ていきましょう。
実際に会社が給料を払えなくなる原因はさまざまです。多くの場合、原因は1つではなく、複数の要因が複雑に絡み合って発生します。ここからは代表的な理由を3つ見ていきましょう。
資金繰りの悪化で余力がない
売上減少や支払いの増加、取引先の倒産などで、会社のキャッシュフローが一気に悪化することがあります。このような状況下では、家賃や材料費の支払いを優先せざるを得ず、従業員への給与支払いまで手が回らなくなるケースが頻発します。しかし、一時的な資金ショートであっても、前述のとおり給料未払いは違法であり、従業員からの信用が失墜したら経営再建のハードルが一層高くなります。
労使トラブル
経営者と従業員、あるいは従業員同士のトラブルが原因で、給与支払いが滞ることもあります。たとえば、業績評価や残業代の未払い、パワハラ問題などから従業員が労基署へ駆け込むことで、会社側が当該従業員に対して支払いを保留・遅延させる場合もあります。一時的な対応としても違法であり、問題の先送りは会社全体の信頼を損なうだけです。
支払い手続き忘れ
一見信じがたいですが、給与計算や振込業務の担当者が多忙である場合や人員不足に起因したヒューマンエラー、あるいはシステムトラブルなどの理由により支払い手続きが正常になされていないケースもあります。特に中小企業では、バックオフィスの業務が属人的になりやすく、誰も気づかず支払いが遅れることもあり得ます。たとえ「うっかりミス」であっても、やはり法的責任は免れません。
給料が払えない場合の2軸の対策
給料が払えない状況に陥った場合、経営者は「資金繰り面」と「従業員対応」の2つの軸で速やかに対策を講じる必要があります。単に資金を調達するだけでなく、従業員の信頼回復や生活防衛も忘れてはいけません。
【会社の資金繰り面】給与を払えるようにするための対策
 給料の未払いを防ぐには、何よりも「資金確保」が不可欠です。社内外のあらゆる資金調達手段を検討し、早急に対応策を実行しましょう。
給料の未払いを防ぐには、何よりも「資金確保」が不可欠です。社内外のあらゆる資金調達手段を検討し、早急に対応策を実行しましょう。
役員報酬の減額・個人的な資産の貸付
まず実施できるのは、役員報酬の減額や役員・経営者の個人資産の会社への貸付です。経営陣が率先して身を切る姿勢を示すことで、従業員の不満を和らげる効果もあります。
個人資産の貸付や役員報酬の減額の交渉は、役員間・株主間の合意が不可欠なので、丁寧に説明し協力を仰ぎましょう。役員や経営陣に交渉する際のポイントや注意点は次のセクションで補足します。
公的制度を利用する
会社が資金ショートした際は、公的制度の活用も重要な選択肢です。状況に応じて、以下のような制度が利用できます。
- 雇用調整助成金制度
業績悪化に伴い一時的に従業員の雇用維持が困難で休業をさせる場合、休業手当の一部が助成されます。 - セーフティネット保証制度
経営が急変した際、信用保証協会が通常枠とは別枠で保証してくれる制度です。資金調達のハードルが大幅に下がります。 - 危機関連保証制度
災害・感染症などの危機的事態に直面した場合に、追加的な信用保証枠が設けられる制度です。 - 未払賃金立替払制度
万が一、会社が倒産した場合、未払いとなった賃金の一部を国が立替払いする制度です。
これらの公的制度は一時的なキャッシュフローの改善や、従業員保護のために有効な手段です。ただし、申請や手続きには時間と労力がかかるため、早めの情報収集と専門家への相談が重要となります。
緊急の資金調達を行う
時間的猶予がない場合には、ファクタリングやビジネスローンなど、緊急性の高い資金調達手段も検討しましょう。売掛債権を早期に現金化するファクタリングや、即日融資可能なローンを活用することで、給与の支払い遅延を回避できる場合があります。これらの資金調達法に関しては以下の記事でもご紹介していますので、ぜひご参照ください。
取引先と交渉する
仕入先や取引先への支払いを一時的に猶予してもらう交渉も手段のひとつです。ただし、取引先との信頼関係を損なうリスクも伴うため、正直かつ誠実に現状を伝え、返済計画や見通しを具体的に説明する必要があります。下手をすれば「あの会社は危ないのではないか」「これからも支払いが滞るのではないか」と思われ、取引が停止される事態も考えられます。交渉は慎重に行い、社内外の混乱を最小限に抑えましょう。
【従業員対応】未払い時の適切な対応と信頼を守る方法
 資金調達だけでなく、従業員への説明・信頼回復も最重要課題です。「何も伝えない」「ごまかす」ことが最大のトラブル要因となります。伝えにくいことではありますが、必ず従業員と向き合いましょう。
資金調達だけでなく、従業員への説明・信頼回復も最重要課題です。「何も伝えない」「ごまかす」ことが最大のトラブル要因となります。伝えにくいことではありますが、必ず従業員と向き合いましょう。
必ず従業員に説明をする
給料が未払い、あるいは未払いになりそうな場合は、必ず従業員に現状を説明しましょう。経営陣が役員報酬を減額したり、個人資産を貸し付けたりしている場合も、全てを包み隠さず伝えることが重要です。従業員の生活がかかっていることを理解し、誠意ある対応を徹底してください。説明を怠り実際に給料が未払いになってしまうと、信頼失墜や一斉退職など、重大な経営リスクが拡大します。
「未払賃金立替払制度」の利用を従業員に促す
会社が倒産し、どうしても給与が支払えない場合、前出の「未払賃金立替払制度」が従業員のセーフティネットとなります。これは、会社が法律上の倒産状態となった際に、未払い賃金の一定割合(80%。上限あり)を独立行政法人労働者健康安全機構が立て替えて支払うという制度です。
利用には条件がありますが、経営者が従業員に制度の存在をしっかり説明し、必要な手続きをサポートする姿勢が不可欠です。申請方法や対象となる範囲など、制度の詳細は厚生労働省や労働局のホームページを参照ください。
従業員への真摯な対応が重大トラブルへの発展を抑制する
給料の未払いは、従業員の離職や訴訟リスク、社会的信用の失墜など、会社存続を脅かす重大トラブルに直結します。逆に、早期の説明や誠実な対応を徹底すれば、従業員も理解してくれ、最悪の事態を防げるケースも多いのです。経営者として“従業員と向き合う覚悟”を決めることがトラブル抑止の第一歩です。
給料が支払えない状態から会社を立て直すために必要なこと
給与未払いが起きたとき、資金繰りや人事労務の課題をその場しのぎで解決するのではなく、会社の「根本」から見直し・再生に取り組むことが不可欠です。ここからは経営改善の具体策について解説します。
経営改善・資金管理体制の再構築
まず取り組むべきは、会社全体の資金繰り管理・財務体質の見直しです。売上の最大化・コストの見直し、無駄な支出の削減、回収サイトや支払いサイトの調整など、あらゆる視点からキャッシュフロー改善に努める必要があります。また、資金管理を「属人化」させず、客観的な視点でチェック・運用できる体制を整えましょう。
人事・給与・勤怠の業務改善と再発防止策
給料未払いの再発を防ぐためには、社内の人事・給与・勤怠管理体制の抜本的な見直しが必須です。
業務フローの効率化、責任者の明確化、IT化や外部サービスの導入なども含め、業務効率化と属人化リスクを低減しましょう。また、特に給与関連の業務については定期的なチェック体制の構築により、支払いミスや遅延、労使トラブルの芽を根本から断つことができます。
倒産・再生・売却など最終手段の判断と備え
すべての努力を尽くしても、給料支払い問題が解消しない場合、会社の存続自体を再検討する必要があります。最終手段としては下記のような選択肢があります。
- 法人破産
会社の清算・法的整理を行い、負債をリセットする方法です。従業員への説明・未払賃金立替払制度の活用が重要となります。 - 事業再生
第三者への事業譲渡やスポンサー支援を受けて再建する方法です。経営改善計画書の策定が不可欠となります。 - 会社売却・事業譲渡
M&Aなどで事業を他社に譲り、雇用や事業の継続を図る手段です。
いずれも迅速な判断と専門家による支援が必須となりますので、早めに相談しましょう。
専門家(弁護士・事業再生コンサル)への相談する
給料未払い問題は、経営や人事・労務の高度な知識が必要で、経営者ひとりで解決できるものではありません。「会社をどう立て直すか」「従業員や債権者にどう説明すべきか」といった悩みも、早期に専門家(弁護士や事業再生コンサルなど)のサポートを得ることで、最適な道筋が見えてきます。また、相談することで経営者ご自身のストレスも軽減できるでしょう。抱え込まず、早めにSOSを出してください。
社員の給料が払えない…そのお悩み「東京事業再生コンサルティングセンター」にお任せください
給料の未払い。それは会社の経営危機であると同時に、従業員や家族の未来を左右する深刻な問題です。しかし、どんなに厳しい状況でも、経営再生への道は必ず存在します。
東京事業再生コンサルティングセンターは、「社歴5年以上+経営者45歳以下」ならコンサル1年無料という独自支援を提供。売上拡大や財務・人事の再生ノウハウが豊富で、企業再生・経営改善計画書の策定から実行まで、事業者様視点で徹底的に寄り添います。
中小企業のあらゆる悩みに向き合ってきた豊富な成功事例と、対応業種の広さが私たちの武器です。「守り」と「攻め」のバランスをとり、優良黒字企業へのV字回復へと導きます。給料未払い・資金繰り悪化でお悩みの経営者様は、一人で悩まず、まずはご相談ください。
«前へ「【税務調査で追徴課税が確定!】払えない時に知っておきたい対処法」 | 「厚生年金が払えない…会社社長が今すぐ取るべき緊急対策を解説」次へ»
本コラムの監修者

事業再生コンサルタント
清水 麻衣子
元銀行マンで、多くの顧客の相手をしてきた実績と数々の中小企業を見てきた知見をもって、東京事業再生コンサルティングのコンサルタントへ。
通常のコンサル会社におけるコンサルタントとは大きく違い、豊富な知識と現場のリアルを把握している、企業を想った本質的なコンサルが魅力。
関連コラム
-
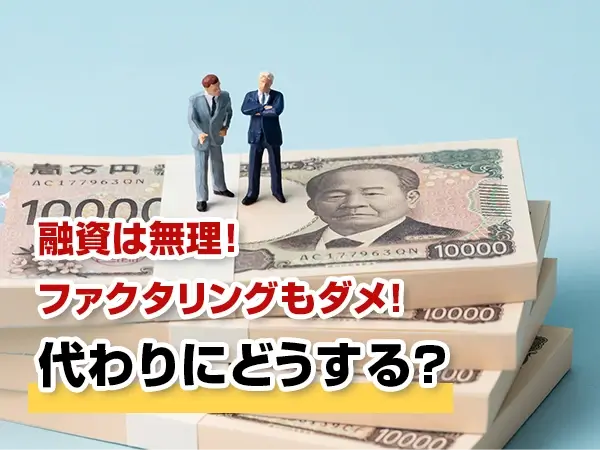
融資は無理!ファクタリングもダメ!代わりにどうする?
-

今すぐ資金繰りを改善したい建設業経営者必見の情報とは
-
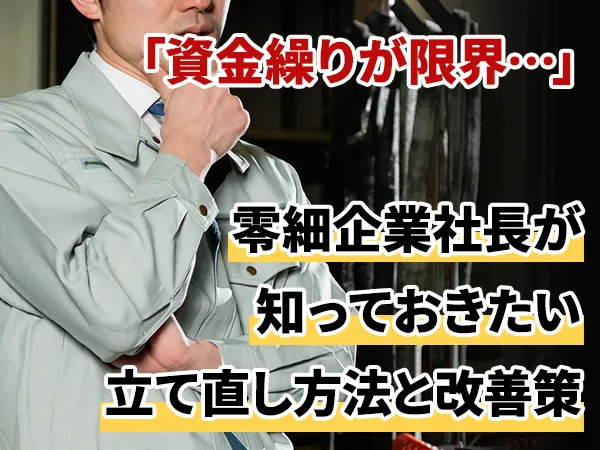
「資金繰りが限界…」零細企業社長が知っておきたい立て直し方法と改善策
-
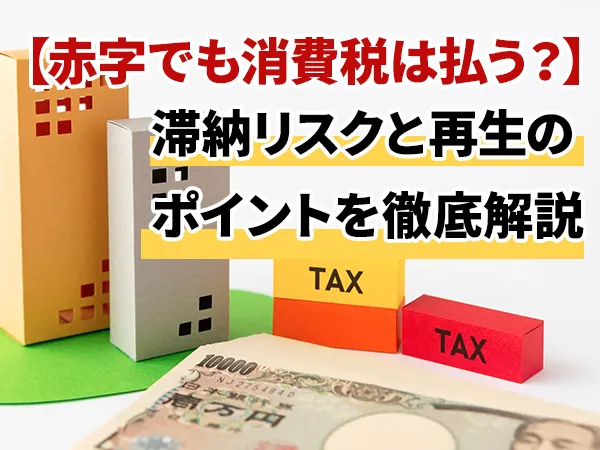
【赤字でも消費税は払う?】滞納リスクと再生のポイントを徹底解説
-
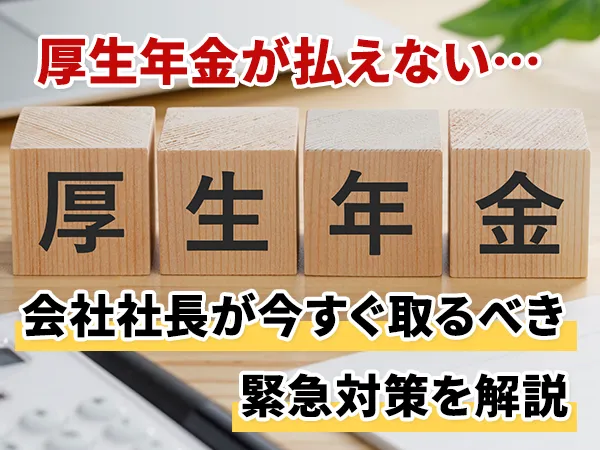
厚生年金が払えない…会社社長が今すぐ取るべき緊急対策を解説
-
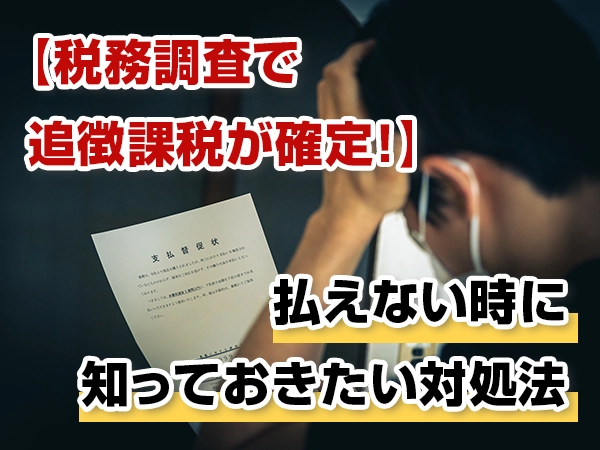
【税務調査で追徴課税が確定!】払えない時に知っておきたい対処法


 1年間無料コンサル
1年間無料コンサル
当社は、若くして起業したり後継者となった方々、本気で事業を立て直したいと強く想っている方々を全力でサポートします。