2025年03月31日
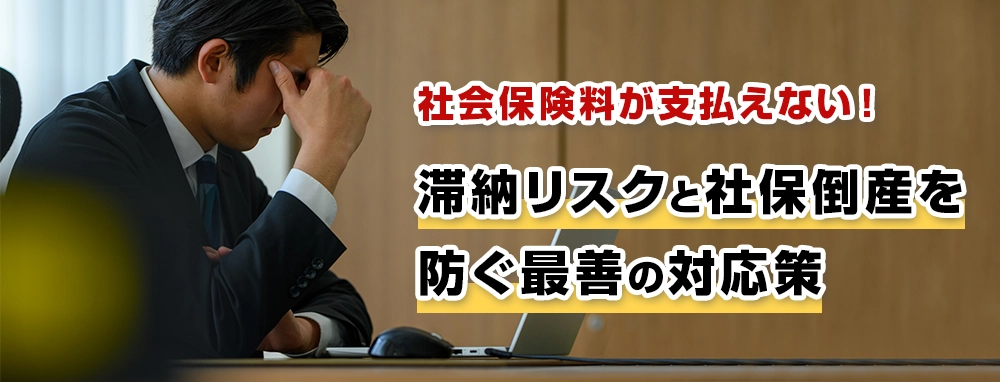
社会保険料(社保料)の滞納は企業にとっては深刻な状況です。放置すれば倒産リスクや信用低下など、さまざまなリスクを招きます。この記事では社会保険料の支払いに悩まれている経営者の方向けに、現状把握から具体的な対処法、さらに事業再生の専門家への相談方法まで分かりやすくまとめました。
あなたの会社は大丈夫?社会保険料支払いチェックリスト
現状を把握するために、まずは社会保険料を無理なく支払えているか、簡単にチェックしてみましょう。もし3つ以下しか該当しない場合は、「滞納リスクが高い状態」といえますので、早急な対策が必要です。
- 会社の銀行口座に、直近3か月分の社会保険料を支払える現金がある。
- 取引先からの入金予定が遅れるリスクはほとんどない。
- 従業員の給与支払いに影響が出ないだけの資金余力がある。
- 直近3か月以内に、税金・家賃・仕入れ代金の支払いを滞納したことはない。
- 追加融資や資金調達の必要性を感じていない。
- 社会保険料の支払いスケジュールを毎月明確に管理している。
- 直近3か月の支払い遅延が一度もない。
- 社会保険料を支払うために他の支払い(仕入れや給与)を後回しにしたことがない。
- 会社の財務状況を定期的に専門家(税理士・社労士)と確認している。
- 直近1年で売上が大幅に減少したことはない。
該当が少なければ少ないほど、現時点ですでに資金繰りにゆとりがない可能性が高いと言えます。社会保険料の滞納は、会社の経営を大きく揺るがす重大なリスク。次章では、社会保険料を支払えない企業が増加している最新の状況を見ていきましょう。
【2025年3月最新】社会保険料滞納による倒産の現状
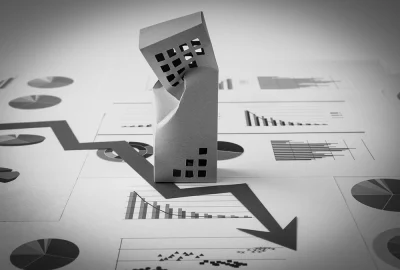 社会保険料を含む公金滞納が原因で倒産してしまう中小企業は後を絶ちません。東京商工リサーチの調査によると、2025年1月~2月における「税金(社会保険料を含む)滞納倒産」は25件発生し、前年同期の約2.2倍に拡大しています。負債総額10億円超の大型倒産も含まれ、状況は深刻です。
社会保険料を含む公金滞納が原因で倒産してしまう中小企業は後を絶ちません。東京商工リサーチの調査によると、2025年1月~2月における「税金(社会保険料を含む)滞納倒産」は25件発生し、前年同期の約2.2倍に拡大しています。負債総額10億円超の大型倒産も含まれ、状況は深刻です。
また、2024年度の税金滞納(社会保険料含む)による倒産件数も、ここ10年で最多とされており、社会保険料の支払いに行き詰まる企業が増えている現状がうかがえます。経済環境の変動やコロナ禍以降の売上低迷などで、十分なキャッシュを確保できず、最終的に支払い不能に陥るケースも少なくありません。
また、社保倒産の増加には、景気の後退や取引先の倒産連鎖だけでなく、社会保険料の負担そのものが大きくなっているという背景もあるようです。次章では、もし社会保険料が払えない状況になってしまった場合、どのような処分やリスクを背負うのかについて解説します。
社会保険料が払えない場合の処分とは
社会保険料の滞納は、単に延滞金を支払うだけでは済みません。国の運営する公的保険制度である以上、企業が負担すべき支払いを怠ると厳しい督促や処分が行われることになります。ここからは、具体的な処分の流れや罰則の可能性について見ていきましょう。
処分の流れ
社会保険料を滞納してしまうと、おおむね以下のようなプロセスをたどることになります。
- 電話や書面による督促 まずは年金事務所などから、口頭や書面での督促連絡が入ります。支払い期日を過ぎると督促状が届くことが多いです。
- 督促状が届く 正式な督促状が届いた時点で速やかに支払いを行うか、納付猶予や分割払いなどの相談に乗ってもらう必要があります。
- 延滞金が発生する 期限を過ぎると一定の割合で延滞金が上乗せされます。放置すれば放置するほど、延滞金が膨れ上がるおそれがあります。
- 滞納処分を受ける(財産の調査・差し押さえ) さらに支払いが行われない場合、財産の差し押さえを含む強制徴収が実施されます。会社の口座、売掛金、動産、不動産などが対象になることもあります。
- (悪質・法令違反の場合は)罰則の対象 滞納が悪質と判断される、または法律に抵触する行為が明らかになると、罰金や懲役などの刑罰にまで発展する可能性があります。
このように、社会保険料の滞納は事態を放置すればするほど厳しくなるのが実情です。
悪質と判断された場合は罰則の対象にも
社会保険料が未納扱いとなり、財産の差し押さえを受ける段階に至っても支払いを行わず、極めて悪質であると当局に判断されれば、健康保険法第208条などに基づき処罰の対象となることもあります。たとえば、不正な偽装工作や支払意志が皆無と見なされるような場合には、罰金や懲役などの厳しい措置が科されることもあるため、軽視するのは禁物です。
倒産しても支払からは逃れられない?!
一部の情報源では「会社を倒産させれば滞納している社会保険料の責任は会社に帰属するので、経営者(社長個人)に支払い義務は残らない」と解説されていることがあります。しかし実際には、社長個人が連帯保証人や個人保証をつけているケースが少なくありません。
倒産して法人が消滅しても、社長個人名義の資産が差し押さえられると、個人として負債を負わなければならない場合が多々あります。一概に「倒産すれば一切の支払い義務から解放される」というわけではないので、軽率に倒産を選択するのは危険です。
延滞金だけじゃない!社会保険料滞納が生む4大リスク
社会保険料を滞納すると多額の延滞金支払いだけではなく、企業再生が難しくなるほどの深刻なリスクを招きます。以下では主な4つのリスクについて詳しく見ていきましょう。
①信用低下
社会保険料を滞納し続けると、会社の財務状況に問題があるとみなされ、取引先や金融機関からの信用が大きく損なわれます。特に銀行やノンバンクは、融資審査の際に会社の納税・社保料支払い状況を重視するため、滞納歴があると新規融資や既存融資の継続が極めて難しくなるのです。
また、信用情報に社会保険料の滞納があった事実が記録されると、経営者や会社の信頼度自体が大きく低下してしまいます。その結果、新たな資金調達ができず、事業運営が立ち行かなくなるケースもあり得ます。支払いが難しい場合は、早期の相談や対策を講じて、信用低下を最小限に抑えることが重要です。
②取引停止
社会保険料を滞納すると、驚くことに年金事務所が取引先に情報開示をすることがあります。「この会社は社会保険料を払っていない」という趣旨の連絡を入れた結果、取引先が会社との取引を敬遠し、事実上の取引停止に至ったケースが報告されています。
国家機関である年金事務所の情報提供に対してやめるように抗議しても、滞納の事実は変えようがありません。取引先からしてみれば、社会保険料の納付ができないほど財務状況が危険な会社とは、継続してビジネスを行うリスクが高いため、結果的に契約打ち切りや支払い条件の見直しなどに踏み切ることがあるのです。これは経営者にとって非常に痛手であり、倒産を加速させる要因にもなり得ます。
③従業員の権利が守られない
社会保険は、従業員が安心して働くための重要な制度です。会社が社会保険料を支払えない状況になると、従業員が健康保険証を使えない、厚生年金が未納となるなど、直接的な不利益が生じる場合があります。
その結果、従業員からの会社への信用が一気に失われ、モチベーション低下や退職者の増加など悪循環に陥ることが考えられます。人材が流出すれば、さらに経営が難しくなり、事業再生の道のりが遠のいてしまうでしょう。
会社を存続させるためにも、従業員の社会保険を確実にカバーすることは経営者としての責務といえます。
④企業責任の追求と世間的イメージの低下
社会保険料の滞納が表面化すると、「この会社や経営者は法令を遵守していない」「従業員の福利厚生を軽視している」といったイメージが広がり、社会的信用を著しく損ねます。マスコミやSNSなどを通じて情報が拡散されれば、取引先や顧客からの批判が巻き起こったり、大衆からバッシングを受けるいわゆる「炎上」という現象が発生したりして、今後の企業活動に大きな悪影響を及ぼす可能性もあります。
このように、社会保険料の滞納は単なる延滞金の問題にとどまらず、倒産リスクから企業イメージの低下まで、総合的に経営を圧迫する要因となります。次章では、滞納を回避しながら資金繰りを改善し、必要な社保料を確保するための具体的な方法を解説します。
資金繰りを改善しつつ社会保険料を確保する方法とは?
 社会保険料の滞納を防ぐためには、まず会社のキャッシュフローを安定させる必要があります。ここからは、具体的な資金繰り改善策や納付猶予制度の活用方法など、事業再生に向けた実務的な対応策を紹介します。
社会保険料の滞納を防ぐためには、まず会社のキャッシュフローを安定させる必要があります。ここからは、具体的な資金繰り改善策や納付猶予制度の活用方法など、事業再生に向けた実務的な対応策を紹介します。
①社会保険料の支払い計画を立て直す
社会保険料を無理なく支払うためには、まず現状を正確に把握し、支払いのタイミングや金額を再計画することが不可欠です。すでに滞納している場合でも、計画的に分割払いなどを検討し、年金事務所や金融機関に相談することで対処できるケースがあります。
支払い優先順位を決める
経営者として、限られた資金を「何に優先的に回すか」を明確にする必要があります。社会保険料の未納が続くと従業員に健康保険証を使わせられなくなるため、最優先で支払い、その次に従業員の給与(未払は労働基準法違反リスク)、そして仕入れ代金やその他経費の順で優先度を決めるのが一般的です。
「とりあえず給与は払うけど、社会保険料は後回し」というケースも多いのですが、最終的に差し押さえや企業イメージの低下など、より大きなダメージにつながりかねません。
②資金調達をする(融資・補助金・ファクタリング活用)
社会保険料の支払いを継続できるだけのキャッシュが不足しているのであれば、融資や補助金、ファクタリングなどを活用して資金調達を行うことも選択肢の一つです。ただし、すでに他の支払いを滞納している場合、銀行融資などはハードルが高くなる可能性があります。信用情報に傷がつく前に、迅速に行動することが重要です。
納付猶予制度を上手く活用する
一時的な資金不足が原因で社会保険料を支払えないときは、納付猶予制度の活用を検討しましょう。年金事務所などに相談することで、一定期間支払いを猶予あるいは分割払いに応じてもらえる場合があります。納付猶予制度を利用するための主な条件例は以下のとおりです(制度によって異なる場合があります)。
- 一時的な資金不足であることを証明できる資料(売上減少の証明など)を提出する
- 国税や地方税での猶予制度と同様に、分割納付や差し押さえ回避のための計画書を提出する
- 以前から継続的に滞納している場合、さらに詳細な事情説明が必要になるケースも
詳しい要件や申請手続きは、厚生労働省や国税庁の公式サイト、もしくは税理士・社労士といった専門家に確認しましょう。早めに相談すれば、罰則や差し押さえといった最悪の事態を避けられる可能性が高まります。
③固定費削減とキャッシュフローの改善
資金を確保するためには、新たに調達するだけでなく、現在のコストを削減してキャッシュフローを改善する取り組みも重要です。たとえば、オフィス賃料の見直しや通信費・光熱費の削減、在庫管理の最適化など、さまざまな策によって経費を削減できれば、その分を社会保険料の支払いに回すことができます。
会社の財務体質を根本から見直してこそ、長期的に安定した企業再生が実現し、社保倒産を回避できるのです。
【社保倒産を防ぐ】自分や会社を破産させないために
ここまで社会保険料の滞納リスクと具体的な対策を見てきました。とはいえ、一時的に支払いを乗り切ったとしても、根本的な解決を図らない限り同じ問題が再燃しかねません。ここからは、長期的に社会保険料の滞納を防ぐための経営戦略や、第三者の専門家への相談のポイントを解説します。
長期的に社会保険料の滞納を防ぐ経営戦略の立案
一度滞納してしまった社会保険料を完済しても、会社の経営状態が本質的に改善されなければ、再び同じ苦境に陥るリスクが高いでしょう。そこで必要になるのが、事業再生を視野に入れた長期的な経営戦略の立案です。
具体的には、利益を生まない不採算事業の整理や、固定費のさらなるコスト削減、資金繰り計画の練り直しなど、会社全体を俯瞰したアプローチが求められます。社会保険料の支払い計画を立て直すと同時に、今後の売上拡大や事業拡張を見据えて、「攻めと守り」の両面から経営戦略を策定することが鍵となるでしょう。
事業の状態を第三者に見てもらう
多くの経営者は、社会保険料の支払いが難しくなるほどの資金繰りに直面しても、社内だけで解決しようとして余計に深刻化させがちです。しかし、会社の弱点は当事者が見落としやすいのも事実。ここからは、第三者に経営や財務状況を客観的に評価してもらう重要性を解説します。
弁護士に見てもらう
弁護士は法的整理や倒産に関するプロフェッショナルなので、債権者との交渉や裁判所を介した再建手続きに強みを発揮します。一方で、法的手続きに特化しているため、事業を継続しながら再生するという視点では、やや範囲が限定される場合もあります。
こちらの関連記事も併せてご覧ください。
中小企業診断士に見てもらう
中小企業診断士は企業の経営改善や収益向上策に精通した国家資格の専門家です。コンサルティングの観点から、具体的な経営計画の策定やマーケティング戦略の見直しなどに強みを持っています。
ただし、法律や債権者交渉、倒産手続きなどのリーガル面は専門外の場合があるため、必要に応じて弁護士や他の専門家との連携が求められます。
詳しくは以下の記事も参考にしてください。
事業再生専門コンサルタントに見てもらう
事業再生を専門とするコンサルタントであれば、企業再生や経営改善計画書の策定において総合的なサポートが可能です。法的整理から資金繰りの再構築、売上拡大ノウハウまで幅広く対応できるため、中小企業が抱える課題に柔軟にアプローチできるのが大きなメリットといえます。
特に、社保倒産を防ぎながら継続事業として再生を目指したい場合には、こうした専門コンサルタントの力を借りることで、最適な解決策を見つけやすくなります。
社会保険料の支払いに関する相談は東京事業再生コンサルティングセンターへ
 社会保険料の滞納は、単なる資金繰りの問題にとどまらず、会社の倒産や企業イメージの悪化、さらには経営者個人への責任追及にもつながりかねません。だからこそ、早期の相談と適切な対応が欠かせます。
社会保険料の滞納は、単なる資金繰りの問題にとどまらず、会社の倒産や企業イメージの悪化、さらには経営者個人への責任追及にもつながりかねません。だからこそ、早期の相談と適切な対応が欠かせます。
東京事業再生コンサルティングセンターでは、事業者視点に立ったコンサルティングを心がけ、「守り」と「攻め」両方のアプローチを用いて事業再生を支援しています。
豊富な成功実績を活かし、幅広い業種にも対応可能。社歴5年以上でかつ経営者様のご年齢が45歳以下の事業者様であれば、コンサル1年無料サービスもご提供しています。
社会保険料が払えないとお困りの経営者様は、お一人で悩まずぜひご相談ください。企業再生に向けた道筋を一緒に切り開きましょう。
«前へ「【経営者必見】債務超過から脱却する方法とは?専門家が解説する再建への道筋」 | 「【徹底解説】ファクタリングが支払えない際のNG行為と対応策とは?」次へ»
本コラムの監修者

事業再生コンサルタント
清水 麻衣子
元銀行マンで、多くの顧客の相手をしてきた実績と数々の中小企業を見てきた知見をもって、東京事業再生コンサルティングのコンサルタントへ。
通常のコンサル会社におけるコンサルタントとは大きく違い、豊富な知識と現場のリアルを把握している、企業を想った本質的なコンサルが魅力。
関連コラム
-
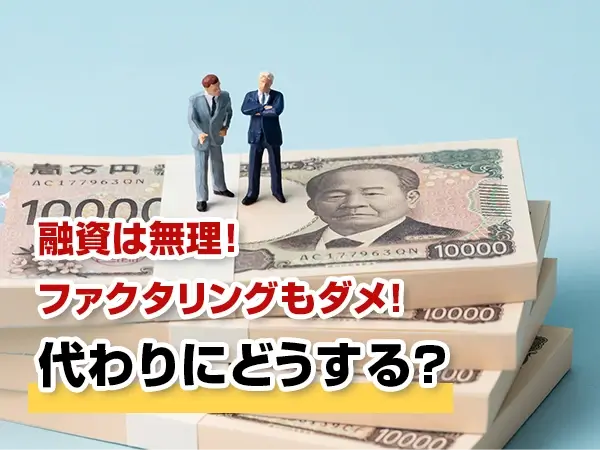
融資は無理!ファクタリングもダメ!代わりにどうする?
-

今すぐ資金繰りを改善したい建設業経営者必見の情報とは
-
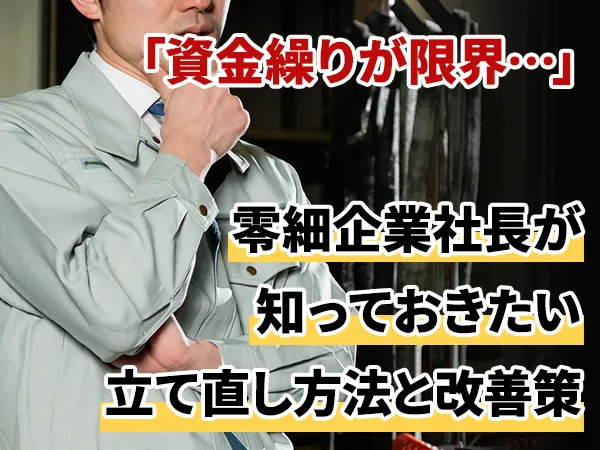
「資金繰りが限界…」零細企業社長が知っておきたい立て直し方法と改善策
-
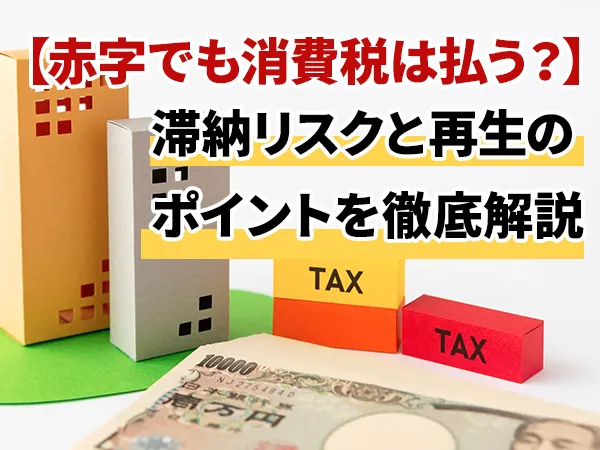
【赤字でも消費税は払う?】滞納リスクと再生のポイントを徹底解説
-
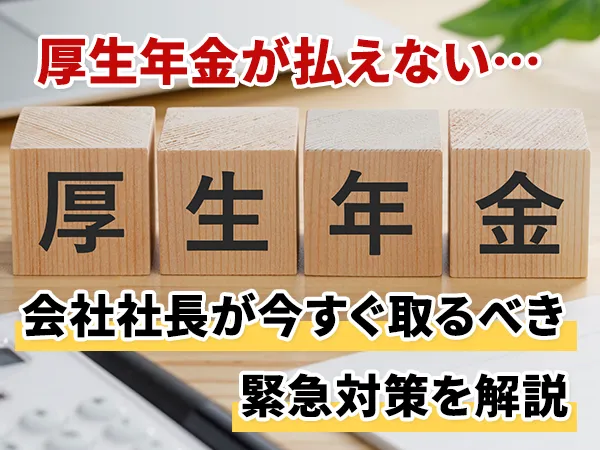
厚生年金が払えない…会社社長が今すぐ取るべき緊急対策を解説
-
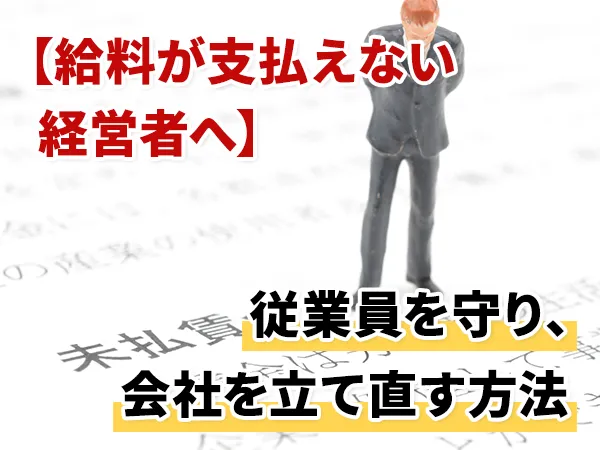
【給料が支払えない経営者へ】従業員を守り、会社を立て直す方法


 1年間無料コンサル
1年間無料コンサル
当社は、若くして起業したり後継者となった方々、本気で事業を立て直したいと強く想っている方々を全力でサポートします。