2025年11月21日
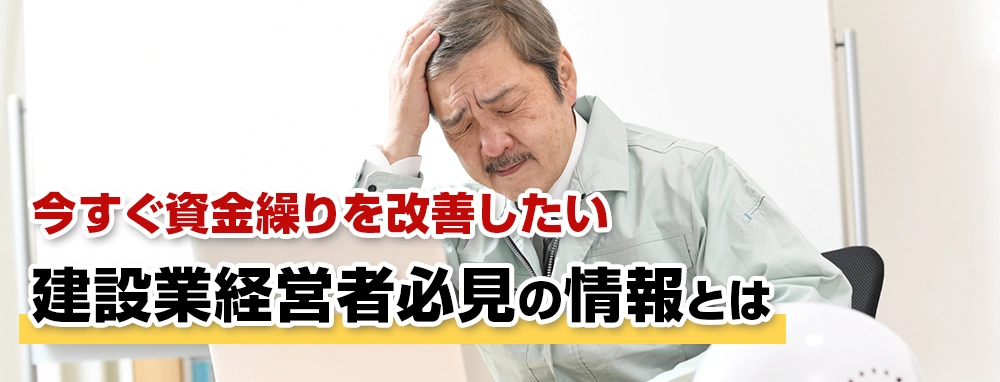
建設業の資金繰りが厳しくなる理由
 建設業はどうしても資金繰りが難しい業種です。利益が出ているにもかかわらず、現金が不足して倒産してしまう、いわゆる「黒字倒産」してしまうケースも少なくありません。
建設業はどうしても資金繰りが難しい業種です。利益が出ているにもかかわらず、現金が不足して倒産してしまう、いわゆる「黒字倒産」してしまうケースも少なくありません。
その背景には、受注から入金までの長期サイクルや、資材・人件費の高騰など、資金繰りを圧迫する構造的な要因があります。まずは、建設業が慢性的に資金難に陥りやすい主な理由を一つひとつ見ていきましょう。
- 先行投資が多い
- 工事原価の管理をしていない
- 銀行の融資が通りにくい
- コストの増幅
- 受注から入金までが長い
- 季節・時期による影響
- 元請けが強い
- 支払サイトを勝手に伸ばされる
- 固定費が大きくなりやすい
先行投資が多い
建設業では、受注を受けた段階で材料の仕入れや外注費、職人の人件費など、多くの費用が先行して発生します。つまり、工事が完了し、発注者から代金を受け取るまでの間は、常に資金が先に出ていく構造になってしまいがちです。
中小の建設会社では自己資金が限られているため、この“先行投資”が資金繰りを圧迫する最大の原因となります。特に複数現場を同時に抱えている場合、手元資金の枯渇リスクが一気に高まります。
工事原価の管理をしていない
工事原価とは、材料費・外注費・人件費・諸経費など、工事に直接かかる費用を指します。これらを適切に管理できていない会社は、気づかぬうちに赤字工事を抱えてしまうケースが多いのが実情です。
特に中小企業では、経理担当が兼務で忙しく、原価の把握が「現場任せ」になっていることも少なくありません。原価をリアルタイムで管理しないと、損益の予測が立たず、資金繰り表も機能しなくなります。
銀行の融資が通りにくい
建設業は業界特有の受注構造と季節変動により、安定的な収益を証明しにくい業種と見られています。そのため、銀行の融資審査においては評価が厳しく、赤字決算や税金滞納があると一気に信用が下がってしまいます。
また、売掛金回収の遅れや工期遅延などのリスクもあるとみなされるため、資金ショートに陥ってからでは融資はほとんど通りません。銀行が貸し渋る傾向がある以上、先を見据えた綿密な資金計画は欠かせません。
コストの増幅
近年、建設業界では資材費と人件費の高騰が大きな問題となっています。鉄筋やコンクリートなどの原材料価格は国際情勢によって変動し、円安の影響で仕入れコストも上昇傾向にあります。さらに、人手不足により職人単価が上がり、外注費も膨らみやすくなっています。
こうした「固定費+変動費」の上昇によって、売上がしっかりと立っていても利益が圧迫され、結果として資金繰りが悪化してしまうケースが非常に多いのです。
受注から入金までが長い
建設業では、契約から請負代金の入金までに数ヶ月から半年以上かかるのが一般的です。さらに、公共工事や大規模案件では完成検査後の支払いとなることも多く、現金化までの期間が極端に長いケースもあります。
こうした「入金までのタイムラグ」が、資金繰りを苦しめる大きな原因の一つです。帳簿に売上が計上されても、実際に入金されなければ資金ショートを防げません。
季節・時期による影響
建設業には季節によって仕事量に波があります。特に冬季や梅雨時期は天候不良で工期が遅れやすく、売上が一時的に落ち込むことも珍しくありません。また、年度末や公共事業の発注時期に業務が集中し、その分だけ資金の出入りが偏る傾向もあります。
こうした季節変動による売上のブレを予測できていないと、支払いが重なる時期に現金が足りず、資金繰りが一気に厳しくなります。
元請けが強い
建設業は下請け構造が当たり前で、元請けの立場が圧倒的に強いことが多いです。そのため、支払条件や納期などが元請け都合で決められ、下請け企業は交渉力を持ちにくいのが現実です。
特に小規模事業者の場合、「次の仕事がもらえなくなる」という不安から、厳しい条件を飲まざるを得ないこともあります。これが結果的にキャッシュフローを悪化させ、慢性的な資金不足へとつながっていくこともあるのです。
支払サイトを勝手に伸ばされる
取引先との関係性が固定化している会社ほど、支払いを一方的に延長されるリスクがあります。元請けが支払いを遅らせれば、その影響は即座に下請けの資金繰りに波及します。
しかし、立場上「取引を切られたくない」と強く言えず、泣き寝入りしてしまうケースが多いのです。その結果、現場に支払う職人の給料や外注費を工面できず、経営が悪循環に陥ります。
固定費が大きくなりやすい
建設業では、事務所賃料、リース料、車両費、保険料などの固定費が多く発生します。加えて、現場が減っても人件費や機材維持費は変わらず支払いが必要です。
そのため、売上が落ち込んだときに赤字へ転落しやすくなります。特に景気や受注環境に左右されやすい業界だけに、固定費をどこまで抑えるかは経営の生命線です。
一般的に謳われている建設業の資金繰り改善方法
資金繰りを改善するための方法は多くの書籍やメディア、専門家によって紹介されていますが、重要なのは「即効性」と「持続性」のバランスを取ることです。建設業は一時的な資金調達だけでなく、日々の入出金管理とコスト管理の積み重ねが欠かせません。
ここからは、一般的によく挙げられる資金繰り改善のポイントを具体的に解説していきます。
代金を早期に回収できる工事を請ける
入金サイトが長い案件ばかりを受注していると、常に資金が詰まりやすくなります。建設業では請負代金の回収時期が案件ごとに異なるため、可能であれば「進捗に応じて分割入金される案件」や「工事完了後すぐに入金される案件」を優先的に選ぶと良いでしょう。
資金繰りに余裕を持たせるには、売上金が現金化されるタイミングを常に意識することが重要です。
入出金管理・原価管理を徹底する
入出金のタイミングを正確に把握することは、資金繰り改善の基本です。経理ソフトやクラウド会計を活用し、現場ごとの収支をリアルタイムで確認できる体制を整えましょう。また、原価管理も同時に行い、どの現場でコストがかさんでいるのかを見える化することが重要です。
毎月のキャッシュフローを把握し、先の支払いに備えることで、急な出費にも対応できる経営体質を築けます。
支払サイトの短縮
仕入先や協力会社への支払サイトを短縮することで、信頼を得ながらコスト削減につなげられるケースもあります。現金払いを選ぶことで仕入値引きを受けられることもあり、結果的に利益率を改善できます。また、元請けとの支払条件を交渉し、できる限り短縮することも有効です。
取引先との関係性を大切にしながらも、自社の資金サイクルを意識した交渉を怠らない姿勢が重要です。
前金の交渉をする
特に新規取引や大型工事では、着工前に工事代金の一部を受け取ることができるケースがあります。前金をもらえると、材料費や人件費を初期段階でまかなうことができ、資金繰りの安定化に直結します。
多くの中小建設業者は「前金を要求しづらい」と感じますが、正当な理由を添えて説明すれば理解されることがほとんどです。遠慮せず交渉し、資金を前倒しで確保する姿勢が大切です。
手形支払いから現金払いへの切り替える
建設業では古くから手形取引が慣習として残っていますが、手形は支払いサイトが長期化しやすく、資金繰りを圧迫します。可能な限り手形取引を減らし、現金払いに切り替えることで、資金の流れをシンプルにできます。
手形の決済遅延や不渡りといったリスクも避けられるため、キャッシュフロー管理の安定化にもつながります。取引先に対しても、透明性の高い経営姿勢を示せるでしょう。
資金繰り表を作成する
資金繰り表は、今後の入出金を可視化し、資金ショートを防ぐための最も基本的なツールです。毎月の支払い予定・入金予定を明確にし、将来の資金不足を早期に察知することができます。
Excelや会計ソフトで簡単に作成できますが、重要なのは「実績との照合」を継続的に行うことです。実際の数値とのズレを修正しながら精度を高めることで、経営判断の信頼性も向上します。
建設業においてはさらに本質的な課題を見るべき
 一般的な資金繰り改善策を実行しても、根本的な経営体質が変わらなければ、またすぐに資金難に陥ってしまいます。特に建設業の場合、表面的な資金管理だけではなく、経営そのものの「構造改善」が必要です。
一般的な資金繰り改善策を実行しても、根本的な経営体質が変わらなければ、またすぐに資金難に陥ってしまいます。特に建設業の場合、表面的な資金管理だけではなく、経営そのものの「構造改善」が必要です。
ここからは、資金繰りを苦しくしている本質的な原因について、実務的な視点から掘り下げて解説します。
人件費の過剰投資と非効率な人材配置
人件費は経営の中で最も大きな固定費のひとつです。現場の仕事量に対して人を抱えすぎていたり、逆に人材配置が偏っていたりすることで、非効率が生まれます。特に多いのは、仕事がある時期に備えて常に多めに雇っているケースです。
従業員は売上を生み出す存在である一方、利益を圧迫する固定費でもあります。外注活用や繁閑期の配置転換など、柔軟な体制づくりが求められます。
見栄による過剰な経費支出
多くの建設業経営者が共通して持つ課題のひとつに「見栄」があります。接待や外食、あるいは高級車や高級時計など、周囲との付き合いや業界内のプライドから高額な出費をしてしまうケースです。
もちろんモチベーション維持や信用形成に必要な部分もありますが、資金難の局面では明確な無駄です。特に事業再生の現場では、こうした見栄による支出が経営を圧迫している例が数多く見られます。経費の優先順位を見直しましょう。
元請けとの交渉、元請けからの離脱
建設業界は多重下請け構造が根強く、利益が上層に吸い取られる仕組みになっています。特に5次請け・6次請けレベルになると、どれだけ努力しても利益が残りません。
元請けからの依存を減らし、自社で直接取引できる顧客を増やすことが、最も効果的な資金改善策です。もちろん、元請けとの関係を維持しつつも、少しずつ「自立型の案件獲得体制」へ移行する努力が必要です。
既に厳しい状況の建設業経営者へ
 建設業の中には、資金繰りの悪化を自覚しながらも「なんとかなる」と放置してしまう経営者の方が少なくありません。
建設業の中には、資金繰りの悪化を自覚しながらも「なんとかなる」と放置してしまう経営者の方が少なくありません。
しかし、気づいたときには税金や社会保険料の滞納、借入金の返済遅延などが重なり、通常の融資もファクタリングも利用できなくなるケースが多く見られます。その結果、家族や知人からの借入に頼り、最終的に身動きが取れなくなることもあります。資金難は“待てば回復するもの”ではありません。早期の相談が何よりも大切です。
すぐに資金繰りを何とかしたいなら
「今すぐに資金を確保しないと会社が止まる」という状況では、理屈よりもスピードが重要です。考えている・躊躇している暇はあまりありません。銀行融資の審査を待っていては間に合わないことも多く、別の資金調達手段を柔軟に検討する必要があります。
ここからは、短期的に資金を確保するための代表的な方法を紹介します。
補助機・助成金の申請
補助金や助成金は返済不要の資金ですが、審査や交付までに時間がかかるため、「今すぐ資金を」という状況には向いていません。とはいえ、長期的な経営改善を目指すならば活用価値はあります。
おまけ程度に考えつつも、国や自治体の制度を定期的にチェックしておくとよいでしょう。建設業でも、省エネ改修やDX関連の補助金が利用できるケースがあります。
ファクタリング
ファクタリングは、売掛金を早期に現金化する資金調達方法です。工事代金の入金を待たずに、請求書をファクタリング会社に買い取ってもらうことで、最短即日で資金を得ることができます。
銀行融資よりも審査が早く、担保や保証人も不要なため、急場をしのぐ手段として有効です。ただし、手数料が発生するため、継続的な利用ではなく、あくまで「一時的な資金難の解消策」として使うのが賢明です。
東京事業再生コンサルティングセンターに相談する
資金繰りの悪化が進行している場合、もはや自社だけでの対応は困難です。東京事業再生コンサルティングセンターでは、建設業の経営改善・債務整理・資金再構築の専門家が在籍しており、状況に応じた再生計画の立案・実行や金融機関との交渉をサポートします。
再建の可能性がある企業であれば、法的手続きに至る前に軌道修正を図ることも可能です。優良黒字企業にV時回復した事例も多数ございます。ぜひ一度ご相談ください。
建設業の事業再生なら東京事業再生コンサルティングセンター
建設業の資金繰りは、構造的に厳しくなりがちです。資金不足の原因を正確に把握し、日々の原価管理・支払管理を徹底することが業績回復への第一歩です。そして、短期的な資金確保策と並行して、本質的な経営改善に取り組んでいきましょう。もし現状が厳しいなら、迷わず専門家に相談してください。
東京事業再生コンサルティングセンターでは、資金繰り表の作成支援から債務整理・リスケジュール・業務改善など、再生に必要な全工程をすべてサポートしています。本気で立て直していただきたいから、1年間は無料でコンサルいたします(条件あり)。取り返しがつかないことになる前に、私たちにお話をお聞かせください。
本コラムの監修者

事業再生コンサルタント
清水 麻衣子
元銀行マンで、多くの顧客の相手をしてきた実績と数々の中小企業を見てきた知見をもって、東京事業再生コンサルティングのコンサルタントへ。
通常のコンサル会社におけるコンサルタントとは大きく違い、豊富な知識と現場のリアルを把握している、企業を想った本質的なコンサルが魅力。
関連コラム
-
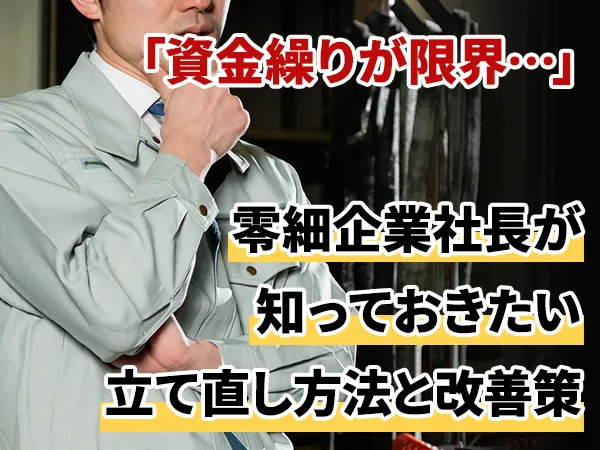
「資金繰りが限界…」零細企業社長が知っておきたい立て直し方法と改善策
-
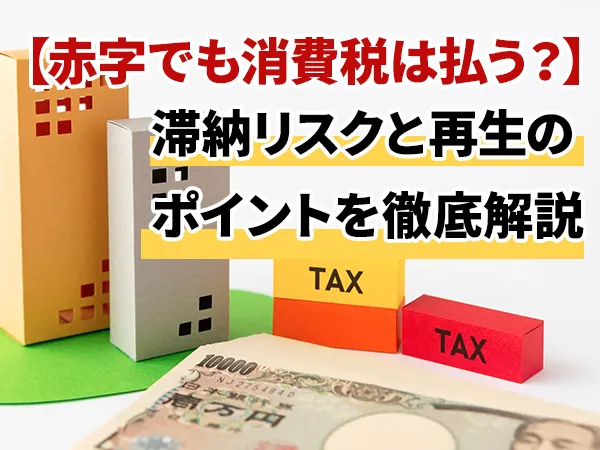
【赤字でも消費税は払う?】滞納リスクと再生のポイントを徹底解説
-
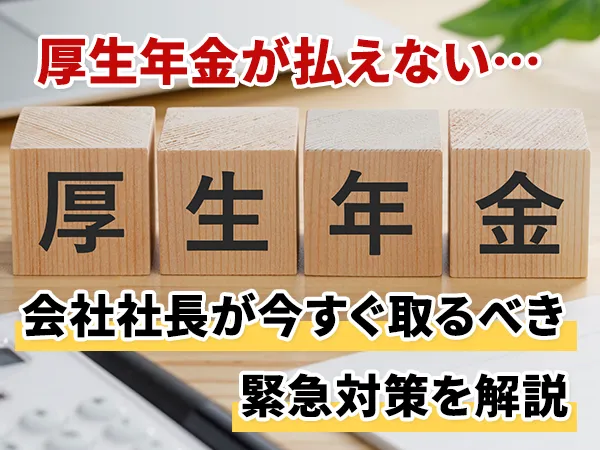
厚生年金が払えない…会社社長が今すぐ取るべき緊急対策を解説
-
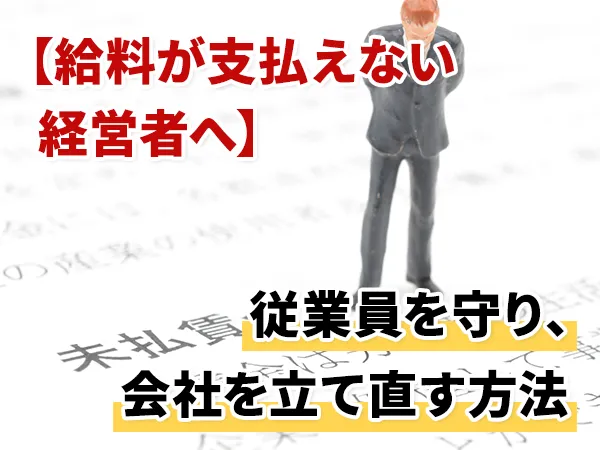
【給料が支払えない経営者へ】従業員を守り、会社を立て直す方法
-
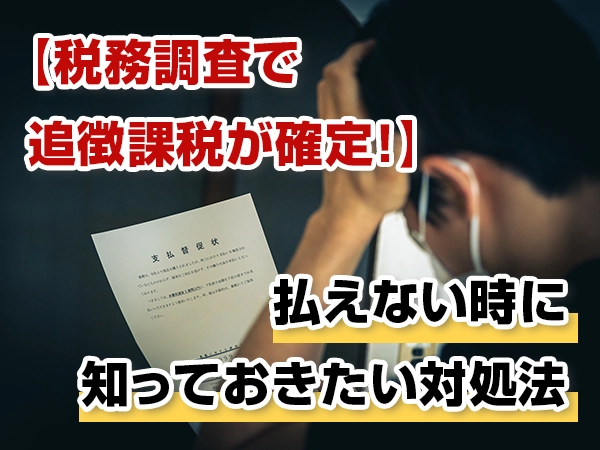
【税務調査で追徴課税が確定!】払えない時に知っておきたい対処法
-
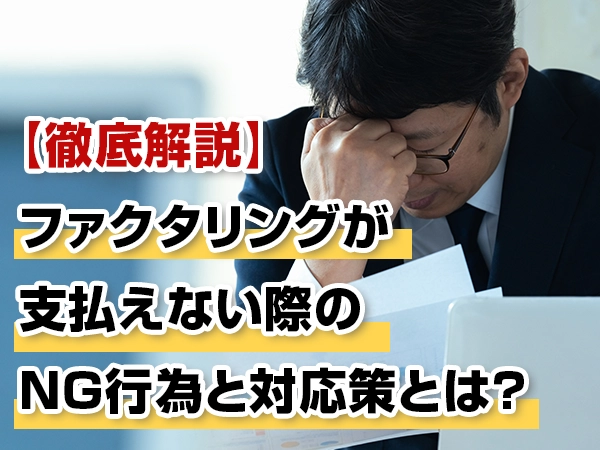
【徹底解説】ファクタリングが支払えない際のNG行為と対応策とは?


 1年間無料コンサル
1年間無料コンサル
当社は、若くして起業したり後継者となった方々、本気で事業を立て直したいと強く想っている方々を全力でサポートします。