2025年06月30日
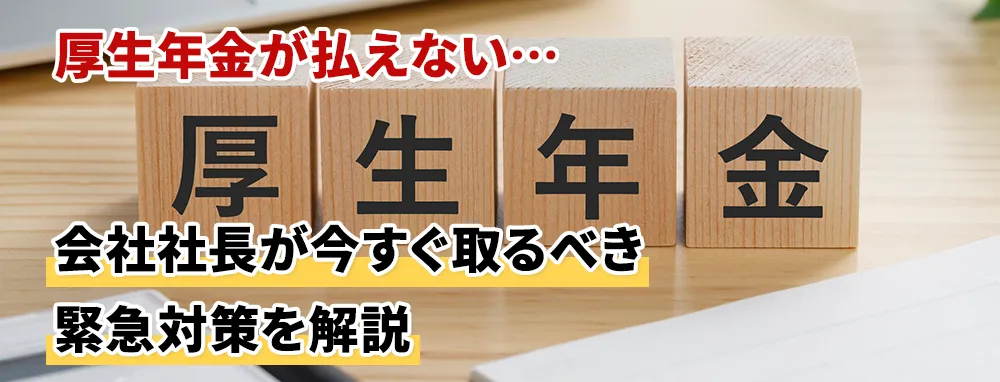
厚生年金の保険料支払いが困難になる場面は、どの企業にも起こりうる経営危機のひとつです。実際に「資金繰りが厳しく、厚生年金の納付ができない」「滞納が続き年金事務所から督促が届いたけど、どうすればいいかわからない」と悩まれている経営者の方も少なくありません。
本記事では、厚生年金が払えないときに企業や経営者が直面する現実、よくある疑問、さらにこれらの対処法をQ&A形式でご紹介します。
【よくあるQ&Aから知る】厚生年金が払えないときの基礎知識
会社の財務が厳しくなって「厚生年金が払えない」と悩まれている経営者の方がよく抱く不安や疑問に対して、その打開策をQ&A形式でご紹介します。焦りや思い込みで間違った行動を取らないために、まずは「何ができるか」「どんなリスクがあるか」を正しく知りましょう。
Q1厚生年金保険料の納付が困難な場合、どのような対応策があるか?
厚生年金の納付が一時的に難しい場合でも、すぐに諦める必要はありません。厚生年金には「納付の猶予」や「換価の猶予」など、事業者の状況に応じた支払い猶予の制度が設けられています。支払いが困難な場合は、まずは年金事務所に早めに相談し、制度を活用して資金繰りを立て直す道を探りましょう。具体的な制度や利用方法については後述の「厚生年金が払えないときの対応方法」の章で詳しく解説します。
Q2厚生年金が支払えない状況が続いた場合、どのようなリスクがあるか?
厚生年金の納付義務は事業主にあり、従業員から天引きした保険料を会社が納めない場合、それは重大な法令違反に該当します。悪質なケース、たとえば意図的に保険料を天引きした上で納付しない場合には詐欺罪や横領罪に問われるおそれもあります。ただし、単なる滞納のみでは原則として刑事罰の対象にはなりません(厚生年金保険法第83条ほか)。
とはいえ、滞納を続けることのリスクは非常に大きいです。まず、延滞金の発生や財産の差し押さえなど、法的な措置が取られる恐れがあります。さらに、金融機関や取引先からの信用が失墜し、追加融資や取引停止といった経営リスクも高まります。信用情報に傷がつくと、今後の資金調達や経営再建も一層困難となるでしょう。
経営者本人だけでなく、従業員にも大きな影響が及びます。従業員側は年金の納付記録が不完全となり、不安や不信感を抱く要因となります。最悪の場合、労使トラブルや従業員の大量離職、訴訟に発展しかねません。このように厚生年金の未納は、企業の存続と従業員の生活を直撃する重大な問題なのです。
Q3年金事務所から督促状や差し押さえ予告通知が届いた場合、どうすればよいか?
年金事務所から督促状や差し押さえ予告通知が届いた場合は、速やかに対応することが最優先です。通常、滞納が一定期間続くと、まず「催告書」や「督促状」が送付されます。ここで対応せず放置していると、次の段階として「差し押さえ予告通知」や「財産差し押さえ」へと発展します。
通知を受けたら、まずは年金事務所へ連絡し、現状の説明と今後の納付計画、支払い猶予制度の利用可能性について相談しましょう。特に、会社の資金繰りや経営状態が厳しい場合には、「納付の猶予」や「換価の猶予」を申請することで、直近の差し押さえを回避できる可能性があります。対応が遅れると、預金口座や売掛金、会社所有の資産が実際に差し押さえられ、事業継続が著しく困難になるため、初動対応の速さが何よりも重要です。
Q4厚生年金の滞納は従業員の年金受給に影響があるか?
厚生年金の保険料は本来、会社(事業主)が納付すべきものです。保険料が滞納状態にあっても、「厚生年金被保険者期間」はそのまま認定されるため、従業員が直接的に年金受給資格や年金額に関して影響を受けることはありません。
ただし、会社が厚生年金を滞納している事実が従業員に知られると、会社への不信感が高まります。「本当に自分たちの年金は守られているのか」「今後会社に未来があるのか」といった不安から、退職者が増加するおそれもあります。こうした場合、経営者としては誠実に現状を説明し、信頼回復と従業員の安心確保に努めることが欠かせません。透明性ある対応と、会社としての立て直し姿勢を示すことが従業員の流出や労使トラブルを防ぐカギとなります。
Q5どの専門家に相談したほうが良いのか?相談するタイミングは?
厚生年金の滞納や資金繰りの問題が生じたら、できる限り早く専門家に相談しましょう。具体的には、弁護士・社会保険労務士・税理士、そして事業再生コンサルタントなど、会社経営と社会保険の分野に強い専門家の力を借りることが重要です。
特に、資金繰りの悪化や社会保険料の滞納は、再発リスクが高い問題です。第三者の目線で自社の経営状況や資金繰り体制を客観的にチェックしてもらうことで、適切な経営改善計画や再生計画の策定が可能となります。専門家のサポートを受けて事業再生・経営改善に取り組むことで、再発防止と企業の信頼回復の両立が実現できるでしょう。
【再確認】社会保険料の中の厚生年金
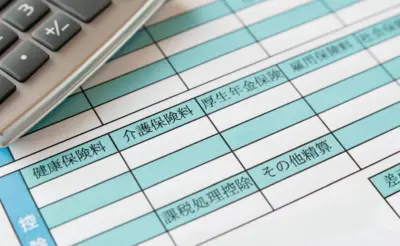 厚生年金保険は、会社の社会保険料の中でも大きな割合を占める重要な負担項目です。社会保険料とは、健康保険・介護保険・厚生年金保険・労災保険・雇用保険などを総称したものであり、これらの保険料は法律により企業の負担義務が明確に規定されています。
厚生年金保険は、会社の社会保険料の中でも大きな割合を占める重要な負担項目です。社会保険料とは、健康保険・介護保険・厚生年金保険・労災保険・雇用保険などを総称したものであり、これらの保険料は法律により企業の負担義務が明確に規定されています。
特に厚生年金保険は、将来の老後資金の根幹をなす制度です。納付義務のある企業にとって、毎月の保険料負担は小さくありませんが、従業員やその家族の生活基盤を支える社会的責任も担っています。ここからは、厚生年金の割合や仕組みを再確認し、会社経営と密接に関わる「厚生年金の重み」について整理してみましょう。
厚生年金の割合
厚生年金保険料の負担割合は、事業主と従業員がほぼ半分ずつを分担する形で決められています(例:保険料率18.3%の場合、会社・従業員それぞれ9.15%)。ただし、納付義務そのものは事業主にあります。会社が従業員から天引きした保険料と会社負担分を、まとめて毎月納付しなければなりません。これが滞ると、会社全体の信頼や法的責任に直結します。
厚生年金が払えないということは社会保険料も払えない!
厚生年金は社会保険料の一部であるため、厚生年金が支払えない状態は「社会保険料そのものが払えない」状況に近いといえます。実際に、厚生年金が払えない企業では健康保険料など他の社会保険料も同時に滞納しているケースが多いです。
こうした場合、社会保険全体の納付遅延が事業存続に重大なダメージとなりえます。。事業再生や経営改善の必要性が高まっているサインでもあり、早期対応が不可欠です。
社会保険全体の滞納リスクや社保倒産については、関連記事「社会保険料が支払えない!滞納リスクと社保倒産を防ぐ最善の対応策」でも詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。
厚生年金が払えないときの対応方法
厚生年金の支払いができなくなった場合、まず取るべき対応は「放置しない」「一人で抱え込まない」ことです。資金繰りや経営状況によっては、納付の猶予や分割納付といった救済措置を受けられる場合もあります。ここからは、実際に選択できる具体的な対応策を見ていきましょう。
厚生年金は支払いの猶予が認められている
経営難や一時的な資金不足で厚生年金保険料が払えない場合、「納付の猶予」や「換価の猶予」など救済制度を活用できます。猶予申請が認められれば、すぐに差し押さえられるリスクを回避しつつ、経営改善に向けた時間を確保することが可能です。各制度には要件や申請手続きがあり、個別の状況に応じたアドバイスも必要になるため、年金事務所や専門家への相談を早めに行うことが重要です。
対応方法①:換価の猶予
換価の猶予とは、すでに差し押さえ処分の段階に進んでいる場合でも、一定の条件を満たせば財産の強制換価(売却)が猶予される制度です。たとえば、滞納保険料の分割納付計画を提出し、その計画に沿って支払いを継続できる見込みがある場合や、会社が倒産寸前ではなく再建見込みがあると認められる場合に利用できます。
この制度を活用するには、年金事務所に「換価の猶予申請書」を提出し、納付計画や経営再建の具体策を説明します。申請が認められると、原則として1年間、財産の強制売却を免れることができます(状況により延長あり)。猶予期間中は、分割納付を誠実に実行し、資金繰りや経営状況を都度報告する必要があります。
ただし、換価の猶予中は、延滞金が一部減免・据置となる場合がありますが、完全に免除されるわけではありません。計画通りに納付できないと猶予が取り消され、即座に財産換価へと進むリスクもありますので、現実的な返済計画の立案が不可欠です。
対応方法②:納付の猶予
納付の猶予は、厚生年金保険料の支払いが一時的に困難な場合に、支払いそのものを一定期間待ってもらう制度です。猶予期間は原則1年ですが、事情によって延長も認められるケースがあります。
申請にあたっては、経営難や資金繰りの悪化などやむを得ない事情が必要です。年金事務所に「納付猶予申請書」や、経営状況がわかる資料(資金繰り表・決算書・納付計画書など)を提出し、担当者と面談を重ねます。納付の猶予が認められると、差し押さえや強制執行を避けつつ、経営再建に向けた時間を確保できます。
納付猶予中も延滞金が発生する点には注意が必要です。特別な事情がある場合は減免の相談も可能です。猶予期間が終了すれば、再び納付義務が生じます。
猶予制度の利用はあくまで「緊急回避策」であり、根本的な経営改善や事業再生が不可欠です。この制度を活用して資金繰りの改善や売上回復を目指し、経営の立て直しに注力しましょう。
経営者として最も重要なのは「早めの行動」
会社経営の現場では、目の前の資金繰りに追われ、厚生年金の支払い問題をつい先送りしてしまいがちです。しかし、未納・滞納を放置することは、経営者自身のリスクを増大させるだけでなく、従業員や会社の未来すら危うくしてしまいます。状況が深刻化する前に、今できる対応から着手することこそが、事業再生の第一歩です。
厚生年金が払えない状況の放置は危険!今できることから始める
 厚生年金の滞納を放置し続けると、差し押さえや信用失墜などの取り返しのつかない事態につながります。会社を守るためにも、従業員を守るためにも、「まずは相談」「まずは行動」が鉄則です。どんなに厳しい状況でも、経営再生の道は必ずあります。自分一人で抱え込まず、専門家や第三者の支援を積極的に活用しましょう。
厚生年金の滞納を放置し続けると、差し押さえや信用失墜などの取り返しのつかない事態につながります。会社を守るためにも、従業員を守るためにも、「まずは相談」「まずは行動」が鉄則です。どんなに厳しい状況でも、経営再生の道は必ずあります。自分一人で抱え込まず、専門家や第三者の支援を積極的に活用しましょう。
「東京事業再生コンサルティングセンター」は厚生年金が支払えない会社の社長・経営者のサポートをしています
厚生年金の滞納は、単なる資金繰りの問題ではなく、会社の根幹を揺るがす重大な経営課題です。しかし、決してあきらめる必要はありません。東京事業再生コンサルティングセンターでは、「社歴5年以上+経営者のご年齢45歳以下の方」という条件を満たしている方であれば1年無料でコンサル提供という独自の支援体制で、再生に本気で取り組む経営者様を全力でサポートします。
私たちの強みは事業者様視点のコンサルティングと、「攻め」と「守り」を両立する再生ノウハウ、そして豊富な成功実績です。業種・規模を問わず、数多くの企業再生・経営改善計画書の策定・実行支援を行ってきたノウハウで、厚生年金の滞納問題はもちろん、売上拡大や企業価値向上にも対応可能です。経営者と従業員の「明日」を守るために、全力でご支援します。
今こそ、経営再生の第一歩を踏み出すときです。厚生年金の滞納や事業再生でお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。
«前へ「【給料が支払えない経営者へ】従業員を守り、会社を立て直す方法」 | 「【赤字でも消費税は払う?】滞納リスクと再生のポイントを徹底解説」次へ»
本コラムの監修者

事業再生コンサルタント
清水 麻衣子
元銀行マンで、多くの顧客の相手をしてきた実績と数々の中小企業を見てきた知見をもって、東京事業再生コンサルティングのコンサルタントへ。
通常のコンサル会社におけるコンサルタントとは大きく違い、豊富な知識と現場のリアルを把握している、企業を想った本質的なコンサルが魅力。
関連コラム
-
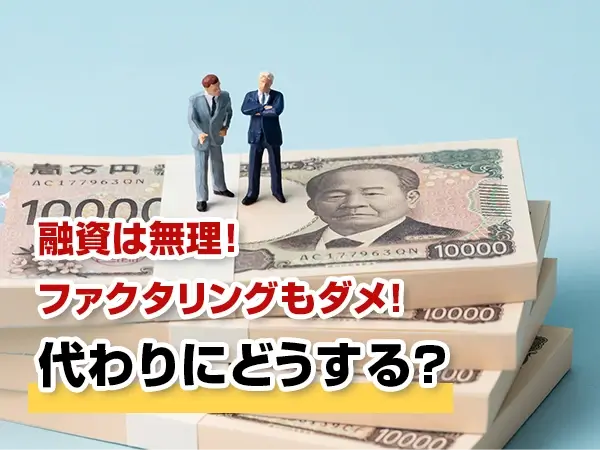
融資は無理!ファクタリングもダメ!代わりにどうする?
-

今すぐ資金繰りを改善したい建設業経営者必見の情報とは
-
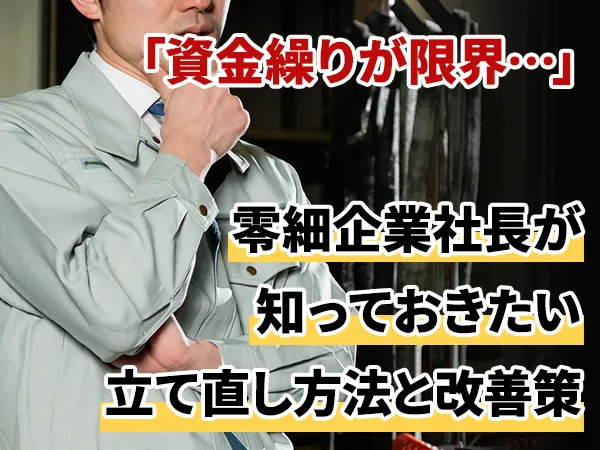
「資金繰りが限界…」零細企業社長が知っておきたい立て直し方法と改善策
-
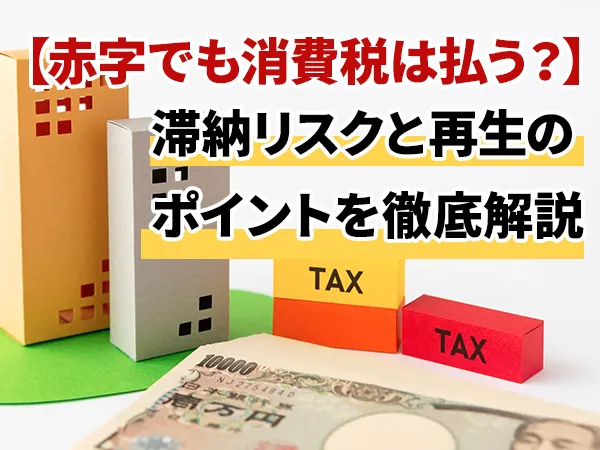
【赤字でも消費税は払う?】滞納リスクと再生のポイントを徹底解説
-
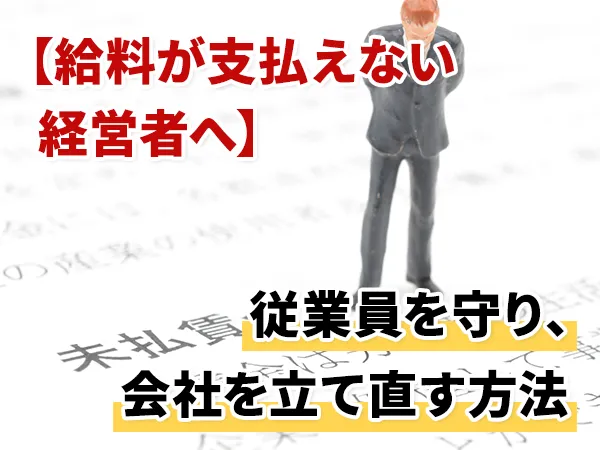
【給料が支払えない経営者へ】従業員を守り、会社を立て直す方法
-
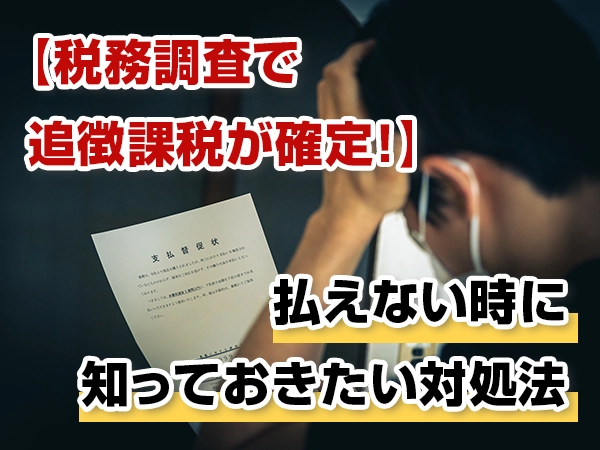
【税務調査で追徴課税が確定!】払えない時に知っておきたい対処法


 1年間無料コンサル
1年間無料コンサル
当社は、若くして起業したり後継者となった方々、本気で事業を立て直したいと強く想っている方々を全力でサポートします。